戦前から戦後へ、
画風を変転させ続けた作家の全貌。
諏訪敦が見た、「阿部展也―あくなき越境者」展
戦前から戦後にかけての美術動向に大きな影響を与えた阿部展也(あべ・のぶや、1913-71)の大規模な回顧展が、広島市現代美術館で開催されている。戦前の前衛写真の運動において重要な役割を果たしたほか、シュルレアリスム、アンフォルメル、幾何学的抽象など、時代を追うごとに画風の変転を遂げた阿部。その歩みを総覧する本展に、画家の諏訪敦が迫る。
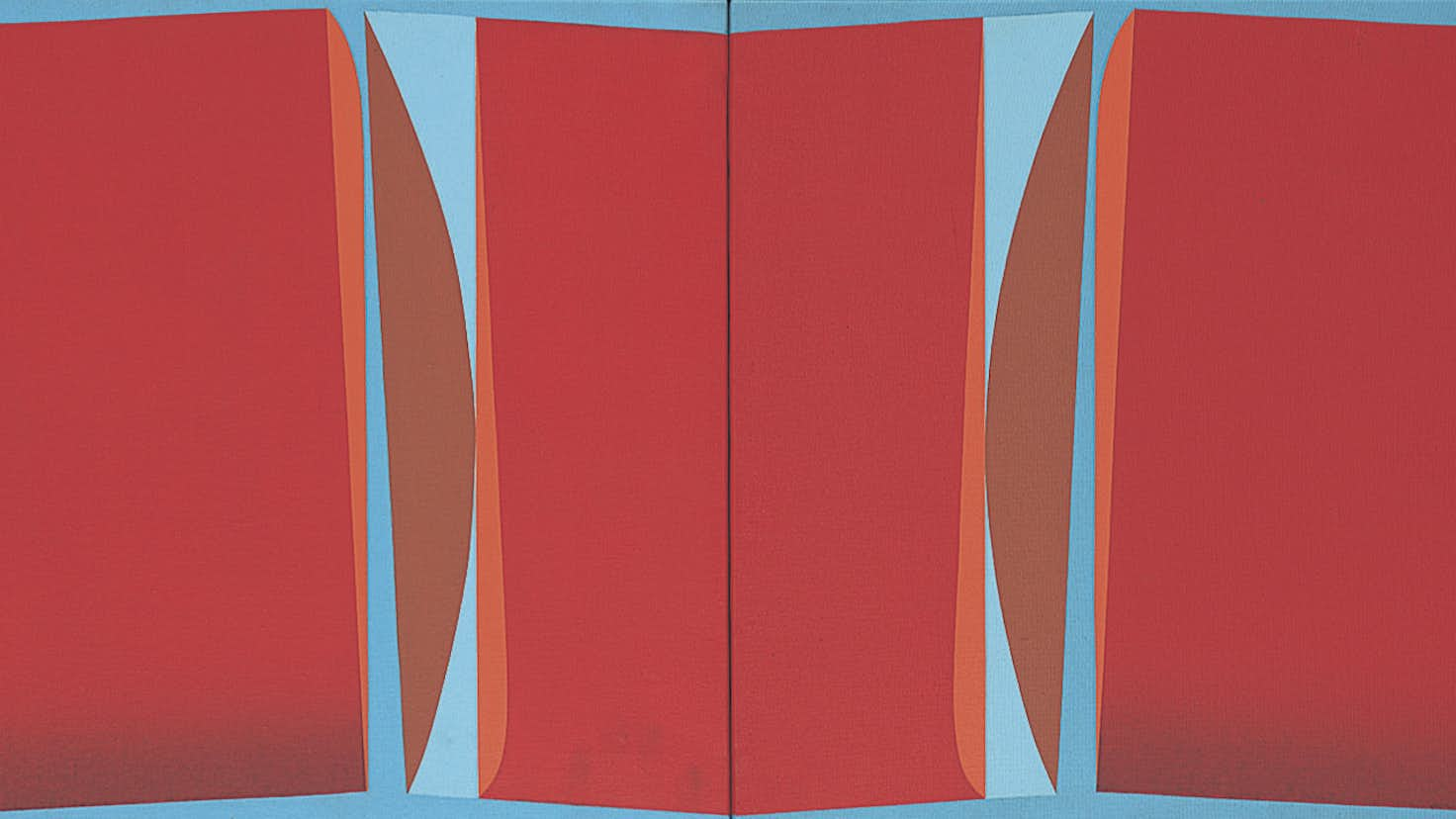
「阿部展也―あくなき越境者」展 越えていくための嗅覚 諏訪敦 評
乱暴に仕分けるなら、アーティストには2種類のタイプがいる。制作態度は泰然自若として変化は少ない者に、時代が追いつき、あるいは移り気な世間の要求とたまたま合致し、やっと評価を受けるタイプ。片や周囲の雲行きに敏感に反応しながら、同時代の先端へつねに食い下がろうとするタイプもいる。強烈なバイタリティと機を見る抜け目のなさが、素養として必須だが、阿部展也は明らかに後者のように見える。
本展のサブタイトルには「あくなき越境者」とある。1913年新潟県に生まれた阿部の仕事を、時系列順に追った回顧展であるが、現代の学生には馴染みがなく、観賞には忍耐を要求されるかもしれない。しかし、戦後日本の前衛(懐かしい響き)の展開に重要な存在であり続けた彼を顧みる機会は、これからも訪れるにちがいない。世界中を渡り歩き、生涯を通して激しいスタイルの変遷をみせた前衛画家の“越境”とはいったい。
1932年の独立美術協会への出品が、阿部の画家としてのスタートであった。初期の出品作はピカソのキュビスムにあからさまな影響を受けた素人絵に見えるが、それは致し方ない。阿部は独学の人であった。それが急に非凡な才能を見せるのは1937年。前年の独立展出品作にも既に、自家醸造したかのような有機的なフォルムが内在していたのだが、瀧口修造との共著『妖精の距離』(1937)でそれは一気に発露することになる。
本展には流動体のような鉛筆による原画が2点展示されているが、この精緻なグラデーションの描写にはちょっと驚かされた。点描でも擦り込みでもない。肉眼で確認できないほどの繊細な線の集積で、この曲線で構成された形態に豊かな諧調を与えている。鉛筆画の解像感は支持体としての紙のテクスチャーに依存するものだが、それを粘着と持ち前の熱量で克服している。
本の構成は、阿部のデッサンに瀧口の詩が呼応するような、見開き12組の作品集になっており、本来、文学が嚆矢としてあったシュルレアリスムが、領域横断的に絵画表現と握手をする理想……それは瀧口の欲望をかたちにしたものであり、現在でも日本のシュルレアリスムの重要な成果のひとつと評されている。その印刷には版の耐久性こそ低いが、網点がないために連続諧調の表現に優れる、コロタイプ印刷が採用された。品位が高く現在も保存修復の分野で活用され続けていて、少部数の限定出版には最高の選択をしたといえるだろう。そして美術家として極めて幸運なスタートに恵まれた阿部は、24歳にして“越境”の果実を口にしていたことになる。

1939年には独立美術協会を脱退し、パリでシュルレアリスムと直に接したという福沢一郎を中心に、阿部は美術文化協会の創立に参加しているが、阿部は日中戦争の拡大が回収不能な様相を見せるなか、フォトタイムス社特派員として旧満洲や内蒙古など大陸北方を旅し、1941年からはフィリピンで日本陸軍の宣撫(せんぶ)工作に士官待遇で従事することになる。それは写真家としての腕を買われてことであり、彼は戦闘員ではない。彼は戦争の記憶を「私の一生にとって裸の動物、利害を異にした動物どうしの、きしきしとひしめきあい爪をたてあう、生き物の能力の限界をテストされつづけの連続であった」と述べているが、(穿った見方ではあるが)彼はやけに生き生きとしているのだ。戦時中、画壇の上位にいた画家たちは、戦争画を描くことでお国にご奉公していたし、日本のシュルレアリストたちは危険思想の信望者として弾圧されていた。そのような状況を他所に、現地の人気女優と結婚し一女をもうけ、フォードを乗り回すなど、阿部の暮らしぶりは相当のものであったようだ。異郷での結婚生活で体得した英語力は、後年、彼を国際舞台へと導く重要なツールになる。
生き残るために発揮された彼の嗅覚とタフさはおそるべきもので、敗戦濃厚な時局、マニラ陥落を察知するや、ルソン島北部の山岳地帯に鞄一杯の札束、持てるだけの財産と食料とともに、家族を連れて逃げ込んでいる。もっとも米軍に捕縛され一家離散、財産は没収の憂き目に遭い、1946年末まで収容所生活を送ることにはなるのだが。
軍の仕事という意味でほとんど絵は描かず、写真撮影と広報に専念していた彼は、意図的であったのかは想像の域を出ないが、結果的に自らの絵画世界を軍に捧げることを避け続けていたのかもしれない。しかしそんななかでも例外はある。1943年に描かれたカソリックの宣撫雑誌『みちしるべ』の表紙原画は、指し示す手(切断した手首)、永遠性を感じる地平線など、シュルレアリスムの象徴的モチーフで構成されているが、マッカーサーを放逐した大日本帝国陸軍の栄光と高揚はなく、画面は不穏さに覆われている。組織に完全には平伏しない阿部展也という人間の複雑さが感じられ、本展中で特に興味深い作品であった。
戦後の阿部は変容を速めていく。戦争責任追及と軍国主義への反省が叫ばれる、一億総懺悔の空気のなか、彼はいち早く培った英語力を活用しGHQ将校と親交を深めるいっぽうで、運動の先達であったはずの福沢一郎を、阿部らは戦争画を描いたという咎で糾弾し、美術文化協会から追放している。自分は軍属であったのにもかかわらず、である。さらには戦場で目撃した記憶であろうか、補給を断たれ飢えや乾きに苦しむ兵士たちを克明に描いた、いわゆる反戦画まで描いているのだが、画面からはある種の空疎さを感じてしまうのは私だけだろうか。

そして主権回復を果たしたばかりの日本人には、海外渡航に様々な制約があった時代、1957年にIAPA(国際造形芸術連盟)の執行役員に座るや、彼はこの職位を渡航理由のお墨付きとしてフル活用し、世界中を飛び回った。翌年にはバルセロナにアントニ・タピエスを訪ね、アメリカではジョン・ケージらと交流するなど、各国の有力な芸術家や美術関係者と交流を続けた。このあたりの嗅覚の鋭さとセンスは天才的で、彼は世界標準の視座を獲得するために行動し続ける。
ほどなく阿部は、海外の先端芸術の実情を知るに至り、戦後、人間を描くことへの強い関心を示し続けていたのに、絵の中に具体的な表象を見るだけで、過去の遺物と感じるようになったのだろうか、具象表現を完全に放棄し、描かれているものではなく、画面の質感〜マティエールを重く見るようになる。60年代には、彼の国際的な評価を決定づけたエンコスティック(蜜蝋を焼き付ける画法)によるアンフォルメル絵画をものにし、のちにアクリル絵具との出会いを経て、晩年のハードエッジな幾何学的抽象の色彩鮮やかな展開に至る。
50歳を目前にした1962年、ローマへ移住し、画業のほかに海外の最新動向を伝えるプロデュース活動も続け、「本場を知る日本人」として本邦の前衛のあり方に影響を与え続けたのは、周知の通りである。
しかし、せき立てられるような変容……この容赦のないスピード感はどうだろう。画家としての評価が停滞するに連れ、阿部の晩年は経済的な困窮と孤独のなかにあったらしいが、一説には1969年頃には、自らの死を予見していたという。戦時下で報道写真に手を染めて以降、異文化のめくるめく刺激の中に身を置き続けていたことは、阿部にとって重要な意味を含んでいる。彼はユーラシア大陸の様々な地域において民族文化の根底に流れる共通性を見ていたし、地理的に巨大な範囲に及ぶ、連帯の思想に魅了されるいっぽうで、日本への批評的な眼差しがつねにあったようだ。
蛸壺化してしまいがちな日本の美術界を脱出し、異質な価値観に自らを放り込むことで見識を押し広げ、世界的視座から日本を、そして自らをとらえ直し、芸術を変革したいという渇望があっただろうし、そのための“越境”ではなかったか。彼は1960年にグッゲンハイム国際美術賞の選考委員に選ばれた際、こう言っている。「僕は若いころから前衛派に入っていて、西欧の自然主義とフォービズムに対する抵抗をやってきたつもりだったけど(中略)民族の中を見ることにより国際的なものに通ずる線、そういうメドが納得する形で出てきました。」……方策として外部から距離を置いて方法論を構築し直そうというのは、誰もが夢想こそはすれ、実行はできないものだろう。しかしそんなときに阿部展也の嗅覚とバイタリティは発揮され、その行動は底光りしていた。まだまだ、世界が広かった頃の話しだ。








