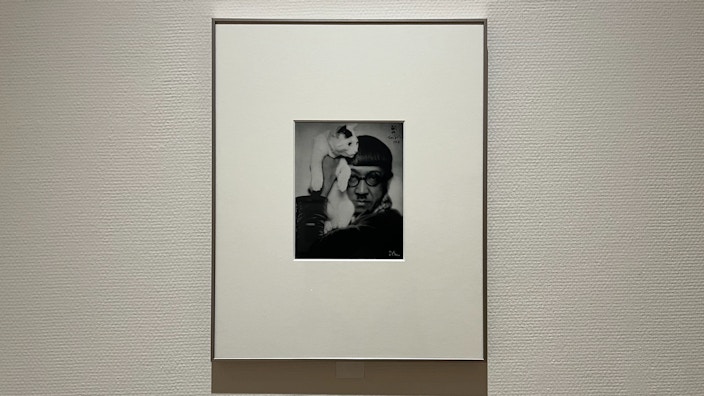櫛野展正連載「アウトサイドの隣人たち」:霧の中から立ち上がる命
ヤンキー文化や死刑囚による絵画など、美術の「正史」から外れた表現活動を取り上げる展覧会を扱ってきたアウトサイダー・キュレーター、櫛野展正。2016年4月にギャラリー兼イベントスペース「クシノテラス」を立ち上げ、「表現の根源に迫る」人間たちを紹介する活動を続けている。彼がアウトサイドな表現者たちに取材し、その内面に迫る連載。第91回は、自閉症スペクトラム症・ADHDと診断された岩田大陸さんが、「半機械」の生き物たちの制作を通じて自身と向き合い続けてきた軌跡について考察する。