シリーズ:これからの美術館を考える(9)
「ブロックバスター展」はどこへ行く?
昨年5月に政府案として報道された「リーディング・ミュージアム(先進美術館)」構想。これを発端に美術手帖では「これからの日本の美術館はどうあるべきか?」をテーマに、様々な視点から美術館の可能性を探るシリーズを掲載してきた。第9回は、数多くの大型展覧会を手がけてきた三菱一号館美術館館長・高橋明也が「ブロックバスター展」のこれまでとこれからを論じる。

「ブロックバスター展」前夜
「ブロックバスター展」について、いざ書こうとすると一見簡単そうで、なかなか語るに難しいテーマだということに気がついた。本来、「ブロックバスター」という言葉は、「街の一ブロックを吹き飛ばす威力のある爆弾」という意味の軍事用語から転じて、大ヒットを生み出す工業製品やイベントについて用いられるようになったものだ。とりわけハリウッドの大作映画などエンタメ系のイベントに対してアメリカで使われ、その後展覧会に関しても時折形容詞として用いられるようになった。私なども何かの折にあえて揶揄を込めて、あるいは挑発的にそう書いた記憶もあるが、結局日本では一般にはさほど定着しなかった言葉だ。
それには理由があるだろう。まず、何をもって「ブロックバスター展」と定義するのか、この出発点からして極めて曖昧である。加えて、あえてそのように呼称しなくても、おそらく日本では、展覧会というもの自体がすでに最初からイベント的な要素を強く持っていたということが言える。もともと江戸時代以来、寺社の「出開帳」というような習慣のあった日本社会で、お宝の出張開陳はじつは馴染んだ形式だったのだ。
とくに「海外から『お宝』を持ってきて数多くの一般大衆の眼に触れさせる」というような、良く言えば啓蒙的、あるいは国際文化交流的なものがおそらく一般市民が持っていた昭和の「美術展」のイメージだったと思われる。さらに、明治期以来根付いた「内国産業博覧会」などの産業博覧会が、ある種の展覧会的な性格を持ち、美術工芸品などを期間限定で見せていたという事実もある。いわゆる「ファイン・アート」や「ボ=ザール(beaux arts)」という「純粋美術」が独立して社会の中で重みを持っていた欧米とは、出発点からして異なっていたのだろう。
第二次大戦後早々に催された「マティス展」や「ゴッホ展」などを皮切りに、日本が高度経済成長に入っていった1960年代以降、すでに海外展は基本的に「ブロックバスター展」とニアイコールの世界だった。テーマ性や作家の評価に関わる内容以前に、どれだけの人が来場し、社会的話題となるかが、新聞社・通信社を中心とする主催者側の最大の関心事だったのだ。
戦後の入場者100万人を越えた主な展覧会を挙げれば、「ミロのヴィーナス展」(1964年、主催:朝日新聞社・国立西洋美術館・京都市美術館、動員数:約172万人)、「ツタンカーメン展」(1965年、主催:朝日新聞社・東京国立博物館・京都市美術館・福岡文化会館、動員数:約295万人)、「モナ・リザ展」(1974年、主催:文化庁・東京国立博物館・国立西洋美術館、動員数:約150万人)、「バーンズ・コレクション展」(1994年、主催:読売新聞社・国立西洋美術館、動員数:約107万人)などである。4つ目は90年代であるが、最初の3つは60年代、70年代に催されている。
その辺のことはあまり突っ込まずとも、80年代後半から90年代のバブル期以降、それまでも我が国で催されてきた大型の美術展覧会が、さらに数を増やし、社会の中で確固とした位置を占めたことは間違いない。これはある意味、時の巡り会わせに過ぎないことだが、私が美術館の世界に入ったのは1980年、東京藝術大学の修士課程を終えて国立西洋美術館学芸課に研究員として勤務したのが最初だった。その後、80年代の半ばに2年近くオルセー美術館の準備室に勤めて帰国したのが1986年、まさに日本がバブル経済に突入する頃である。
そして帰国後に、日本でそれまで行われてきた海外展を凌駕するような大規模な展覧会をいくつもすることになった。ヨーロッパ評議会と読売新聞、国立西洋美術館が共催した「西洋の美術:その空間表現の流れ」展(1987年)などはそうした典型であろう。
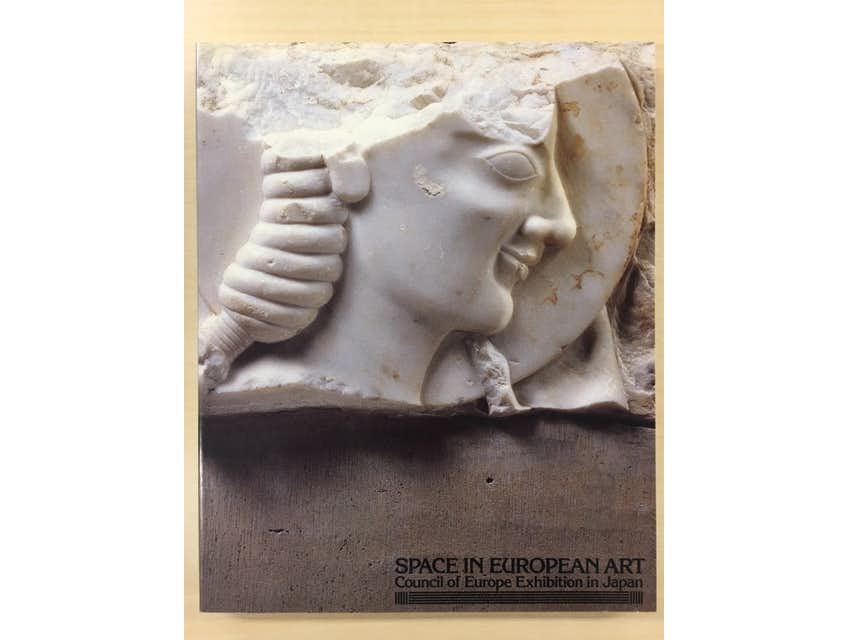
とにかく大型の展覧会であり、それだけでなく、ルーヴル美術館(パリ)やアルテ・ピナコテーク(ミュンヘン)、ブレラ美術館(ミラノ)、プラド美術館(マドリード)をはじめ、ヨーロッパの著名美術館を中心に多くの美術館・所蔵家が参加し、一般向けとはいえ筋の通ったテーマ性も備えていた。各館長や研究者たちを招いてシンポジウムをするなど、私の知る限りそれまでの我が国で最も大規模な西洋美術の展覧会で、古代ギリシャの彫刻から中世の「ブーシコーの時禱書」、貴重なデューラーやマンテーニャ、ティツィアーノなどのルネッサンス期の名作、17世紀のフェルメール、ベラスケス、プッサンを経て19世紀のターナー、マネ、さらにキュビスム前後の20世初頭の変革期の実験的諸作品にいたる展示作品は質も極めて高く、61万人以上の観客を集めた。
また、伝説的とも言える「ジャポニスム展:19世紀西洋美術への日本の影響」(1988年、主催:国立西洋美術館・国際交流基金・日本放送協会・読売新聞・フランス国立美術館連合・オルセー美術館、動員数:約46万人)は、オルセー美術館と国立西洋美術館の学芸員が中心となり、日欧の美術史研究者たちの研究成果を纏めながら文字通り共同でつくった展覧会であり、基本的には、欧米の研究者や美術館が展覧会の監修を行い、日本側は受身だった日本の西洋美術展の歴史でも画期的だったと言えよう。
そして、その翌年に私が初めて単独で担当してつくり上げた「ドラクロワとフランス・ロマン主義」(1999年、主催:国立西洋美術館・東京新聞・名古屋市美術館、動員数:約18万人)も、新聞社の文化事業部と美術館による日本側のマネージメント・チームとジャック・テュイリエ・コレージュ・ド・フランス教授が共同で実地調査を行いながら長い時間をかけて構想・制作した、手づくり感満載の国際展覧会となった。
この頃の展覧会は、上り坂の日本経済を背景に、我が国の資金力とマネージメント力、企画内容のバランスが取れていた時期とも言える。さすがに、かつて私が先輩学芸員から聞いた、「展覧会は年に一度のお祭りなんだから、楽しまなくちゃ」というような1970年代以前の牧歌的雰囲気はもはや消えていたが、かといって昨今の収支と入場者の数字に血眼になっているビジネス・モード全開というわけでもなかったのだ。それゆえ、筆者としてはこの時期の大型展を「ブロックバスター展」と呼ぶのは若干憚られる。意識的・無意識的にかかわらず、メディアの人たちを含めた関係者の多くが、文化交流・国際親善のツールとしての過去の展覧会形式から脱し、それなりに国際レベルの本格的な内容の美術展開催を目指した時代だったからだ。

重視されはじめた「コスト・パフォーマンス」
問題は90年代になってからであろう。これも様々な経緯からたまたま私が担当したわけだが、名高い「バーンズ・コレクション展」(1994年、主催:国立西洋美術館・読売新聞社)には107万人以上の観客が押し寄せ、一種の社会現象としても大きく報道された。カタログも40万を超える部数を売り上げ、結果的に素晴らしい収支となったことは記憶に新しい。
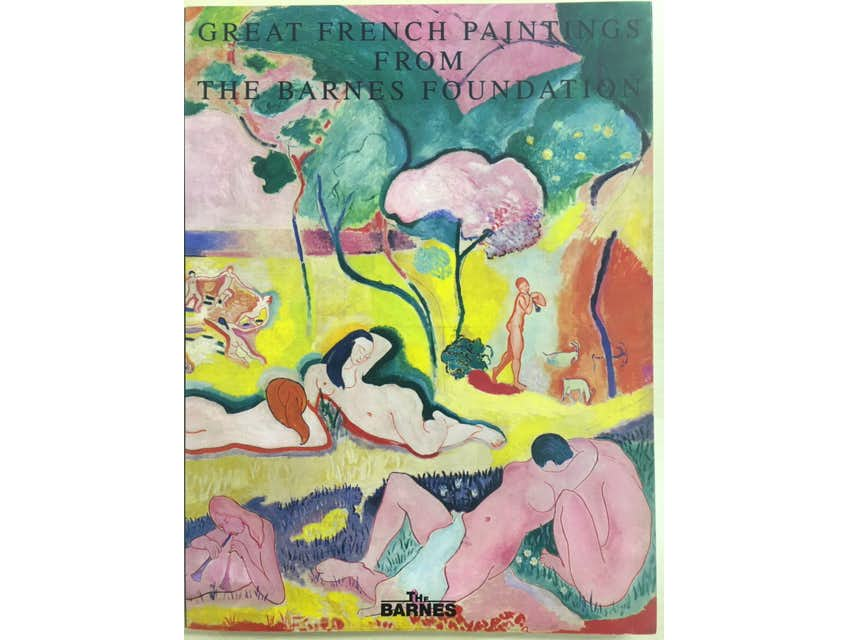
すでに社会的にはバブルの崩壊が訪れ、さすがの日本経済も青息吐息になっていた。他方で海外の美術館の経営は時を追って逼迫し、次第にジャパン・マネーを狙って日本などに展覧会を輸出して稼ぐ体制をどこも取ろうとしてくる。ところが実際には、肝心の日本の主催者側の懐は急激に悪化を始めていた。そして誰もが、「バーンズ・コレクション展」の興行的成功をひとつの道標にして、できるかぎり安価な投資で展覧会を組み立て、高いリターンを得ようという、「経営」に飛びついたのだ。その結果、大型の「○○美術館展」が横行するようになった。
それらを総称して「ブロックバスター展」と呼ぶのは可能な気がする。もちろん、真面目につくられた展覧会も多く、手前味噌だが、私も3回(1996年、1999年、2005年)の「オルセー美術館展」(主催:東京都美術館・国立西洋美術館・神戸市立博物館・日本経済新聞社)などでは、新聞社サイドや先方の学芸員たちと十分にコミュニケーションを取って、たんなる名作選ではなくそれなりに深いテーマ性を帯びるように工夫したものだ。
他方、それらしいタイトルが付いていても、実際にはお手軽に収蔵庫にあって陽の眼を見ない作品ばかりだったり、日本向けの海外巡回用作品のみで組み立てられていたり、この頃の海外展(俗に「引越し展」という言い方もされていた)は文字通り千差万別の内容である。展覧会も経費と収益のプラス・マイナスの金銭的裏づけが必要なのだから、ビジネスとして考えれば当たり前のことなのかもしれないが、それが露になったのがこの頃のことだったように記憶している。
当時の国立美術館は一種の貸し会場化していて、一学芸員として働いていた身では内容にタッチはするが詳細な経営収支は分からない仕組みだった。とはいえ、もとより実際にはこれほどリターンの内容が不確かで利潤の薄い仕事も少ない。社会貢献的マインドや、美術展を見たことが将来長きにわたって少しずつ一人ひとりの身に沁みてくる夢を信じていなければやっていられない文化的営為ではないだろうか? その意味では、「バーンズ・コレクション展」以前にはまだ、各新聞社の文化事業担当者のプライドを賭けた「社会貢献」の競争が、痩せ我慢をしつつ成立していたような気がする。
しかし最近では、筆者などはつい「それほど収支が気になるなら、最初からお止めになったほうがいいのでは?」と禁句を言ってしまいそうになり、慌てて「いやいや、お金は大切だし、そうは言っていても皆、本当はいい展覧会をやりたいんだ」と思い直すような場面が多くなっている。
「○○美術館展」の終わり
しかし結論的に言えば、海外の美術館が文化交流という名目で、友好的に日本に著名作品を貸してくれる時代はほぼ終わったと考えて間違いない。アメリカの美術館の多くは、ボストン美術館などを筆頭にかなり以前からビジネスライクだったが(そうしたなかでも、ワシントン・ナショナルギャラリーやフィリップス・コレクション、フィラデルフィア美術館など、いくつかの美術館はむしろ友好的であったことを思い出す)、フランスなどはわりと最近まで「文化大国」「美術大国」の意識をもって(多少、上から目線のきらいはあったが)、自国の文化遺産の香りを極東の島国の人々にも是非嗅がせてあげよう、というくらいの余裕で作品を貸してくれたりもした。

筆者の友人でもあるアンリ・ロワレット(元オルセー美術館、元ルーヴル美術館館長)なども「必要以上のローン・フィーは取りたくない」とかつて殊勝に語っていた。でも21世紀はもうその時代ではない。まず、この社会不安の多い時代に、純粋に作品保存の観点から見れば、輸送・展示に伴う不慮の事故以外にも、テロや戦争など、リスク過多な海外への輸送・展示などあり得ないことだからである。それをあえてするのは、一様にどこの国でも美術館の予算が削られている事実を踏まえたマネージメント的立場からの要請ゆえなのだ。
かつて、ボストン美術館に知り合いの学芸員(あえて名は伏せるが)を訪ねたときのことを思い出す。こちらが企画していた展覧会の意義・内容を説明し、大いに賛同された後、突然マネージメント担当者にバトンタッチされ、「後は彼女と話し合ってくれ」と言い置いて彼は立ち去り、その後はひたすら金銭的交渉をせざるを得なかった。
そしてさらに、画集や海外旅行で見た海外の有名美術館の所蔵品を確認して満足したりする、単純な「○○美術館展」ではもう、大量動員は難しくなっている気がする。例えば、この秋開いたばかりの「フェルメール展」(主催:上野の森美術館・産経新聞社・フジテレビジョン・博報堂DYメディアパートナーズ)などは、この寡作な画家の作品を9点あまり集めて、膨大な観覧者を呼び込もうとしているが、こういうものは、フェルメール人気をシンプルに前面に押し出した新世代型の「ブロックバスター展」と言えるのかもしれない。何十年か前に、初来日したマウリッツハイスの《真珠の耳飾の女》に付き添ってゆったりと国内を旅した身からすると、昨今のフェルメール人気の一般への浸透振りには心底驚かされる。
ともあれ、セキュリティー・リスクの高まりによる近年の保険料、運送費の高騰や、ツーリズムの世界的広がりに由来する人気作品の移動の鈍化などを考えると、ブロックバスターであろうとなかろうと、いままでのような「出開帳」的な西洋美術の展覧会はもう成立しなくなってきているのが現実なのだろう。逆に、様々な工夫を重ね、いっそうの努力をして新たな分野に視野を広げ、新鮮な切り口で展覧会を組み立てていかないことには、建設的な将来はないように思える。
つい先日も、ふと開催中の公共美術館での展覧会リストを眺めていて、改めて確認したことがある。10数本程並んでいる展覧会のうち、海外の作品を集めたものは3例ほどにすぎず、いずれも作家の回顧展で、2つは19世紀と20世紀のデザイナーの、そしてもうひとつは美術史上の著名作家のそれだった。たまたまだったのかもしれないが、いわゆるブロックバスター的「○○美術館展」は皆無だった。その代わり(と言ってはなんだが)全体には日本の古美術や現代作家の回顧展やテーマ展が増え、同時に「○○神社」「○○寺」の名を冠した「出開帳展」的なものが増えている。
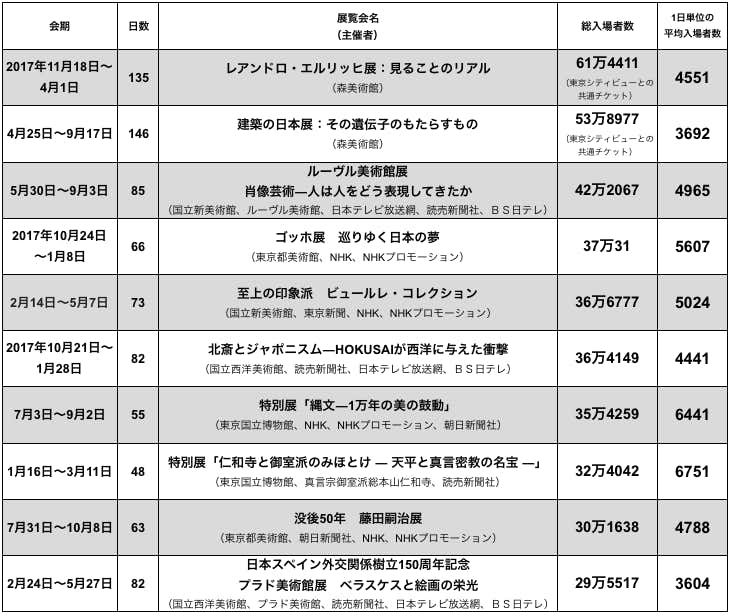
誤解を恐れずに言えば、過去の大規模な海外美術館展に代わって、このような日本美術の「出開帳展」が新しいかたちのブロックバスター展になりつつあるのではないか。ちなみに、2009年に東京国立博物館と九州国立博物館で開かれた「興福寺創建1300年記念『国宝 阿修羅展』」(主催:東京国立博物館・九州国立博物館・興福寺・朝日新聞社・テレビ朝日)には、2会場で165万人以上の入場者があったと聞く。日本美術に眼が向かうこと自体は日本人として慶賀であり、ようやく入超の時代が終わって正常の状態になった感があるが、それがまた、イベント志向の「いつか来た道」にならないように留意する必要はあるだろう。
本来、恒久的な不動のものよりも、時間的・季節的な制約のある、すなわち「旬」のものを好む日本人の感性もあり、短期間のお祭り的性格を持つ「展覧会」という形式は明らかに我々の感受性にフィットしている。それがすなわち、「入場者数」と「集金」のみに集約されないことを願うばかりだ。





