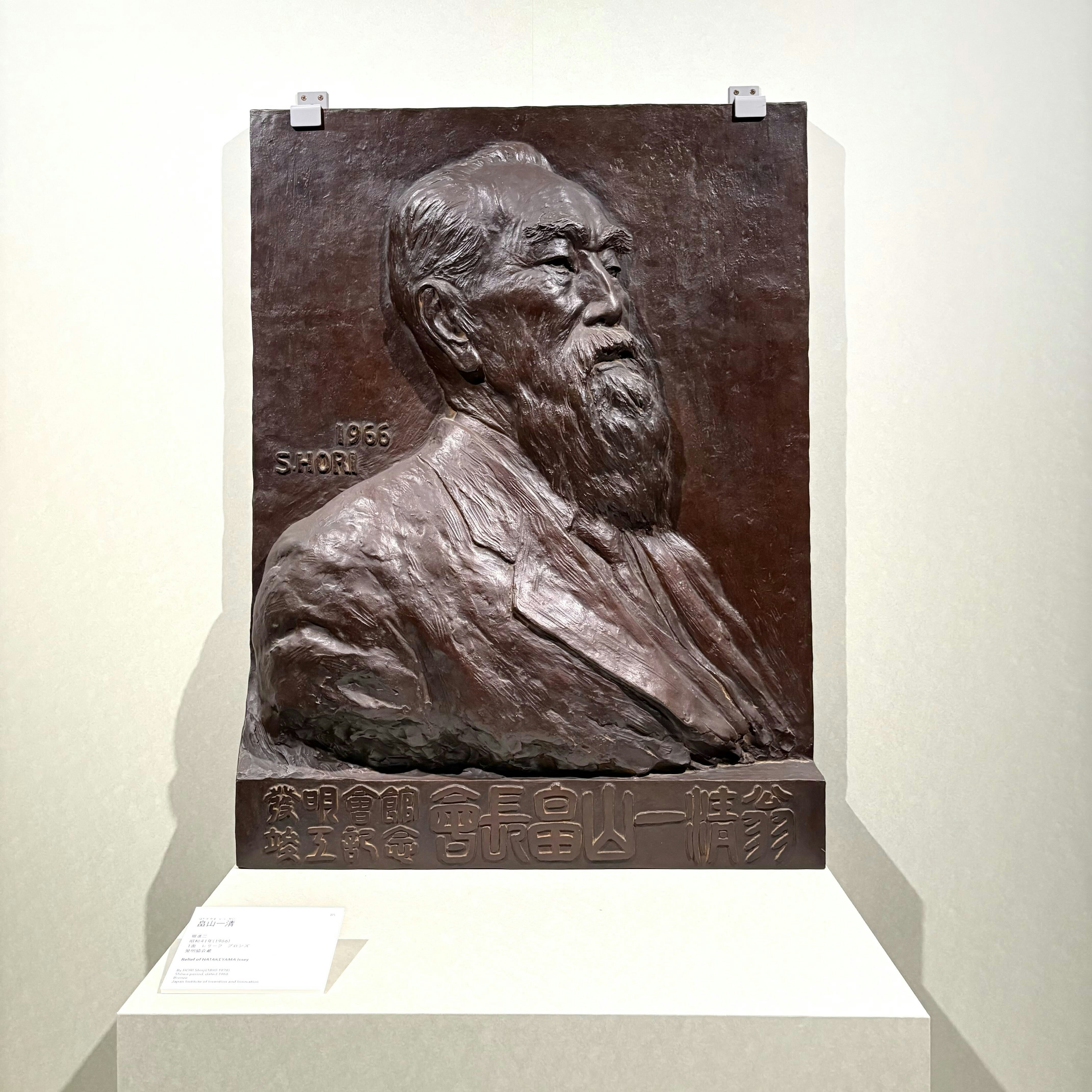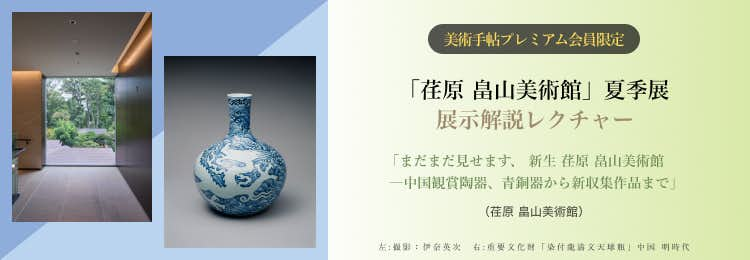「まだまだ見せます、新生 荏原 畠山美術館―中国観賞陶器、青銅器から新収集作品まで―」(荏原 畠山美術館)開幕レポート。幅広いコレクションのなかで涼を味わう
東京・白金にある荏原 畠山美術館で「まだまだ見せます、新生 荏原 畠山美術館―中国観賞陶器、青銅器から新収集作品まで―」が開催されている。会期は9月15日まで。

東京・白金にある荏原 畠山美術館で、同館収蔵品の魅力を伝える展覧会「まだまだ見せます、新生 荏原 畠山美術館―中国観賞陶器、青銅器から新収集作品まで―」が開催されている。会期は9月15日まで。
本展は、2024年10月から3期に分けて開催された開館記念展に続くもの。同館が所蔵する重要文化財や国宝をはじめとし、新収蔵作品も紹介される貴重な機会となっている。3期までに紹介できなかった作品も展示されることから、展覧会名には「まだまだ見せます」と同館の意気込みが感じられるようなフレーズが入っている。
全3章で構成される本展。1章「涼を味わう―東洋のやきものと書画」 は、本館2階展示室で開催されている。自然光を取り込む構造の展示室となっており、この時期の強い日差しも障子を通すことで柔らかくなり、会場全体が心地よい明るさになっている。
夏の暑い時期に行う茶事(少人数で行う茶会)には、涼しさを演出するための様々な工夫がされてきた。本章では、焼きものや書画、茶器など、茶人が涼を感じさせるために凝らした工夫がつまった作品が展示されている。