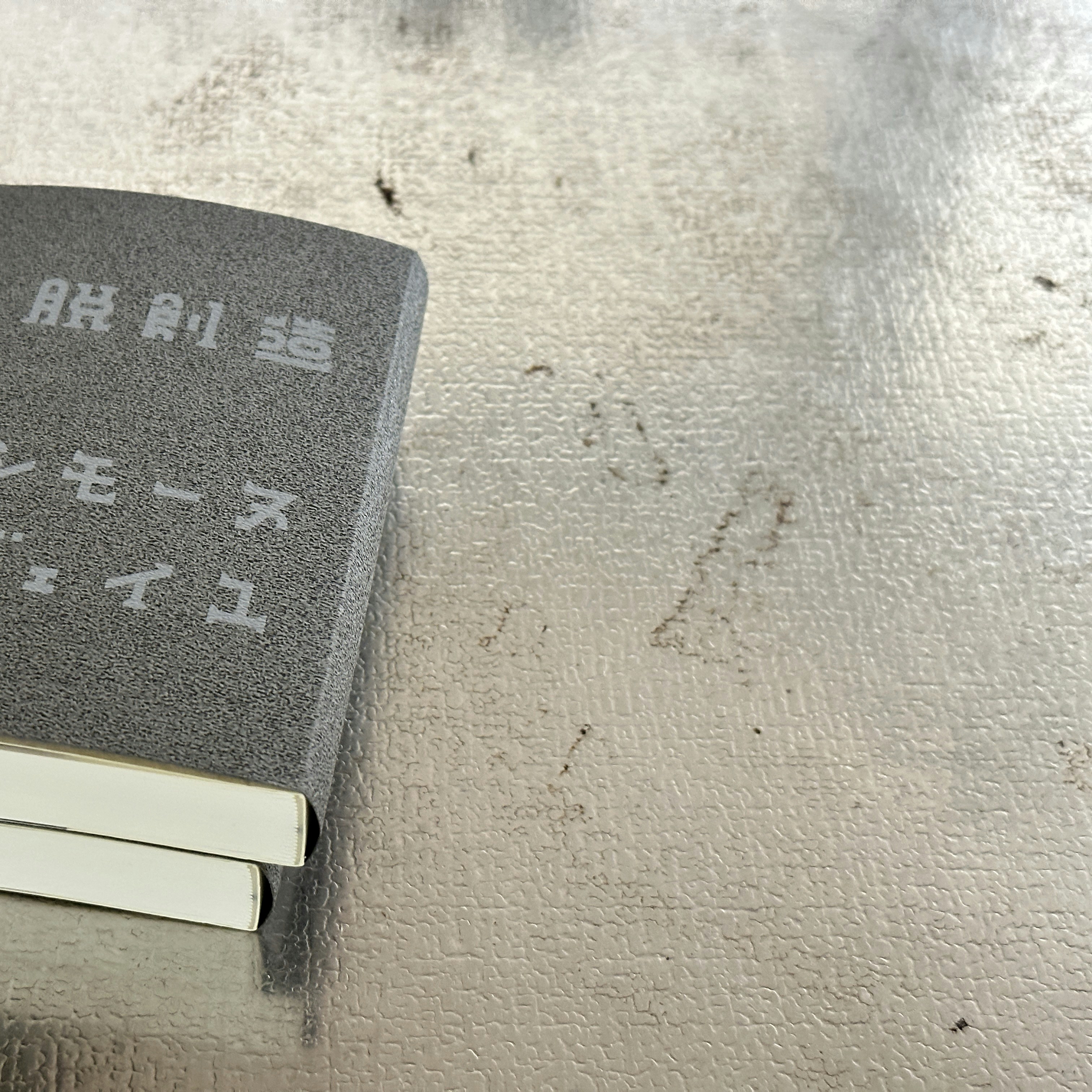「岡山芸術交流2025」の見どころは? 「青豆の公園」でつながる非日常と日常
岡山市内を会場に3年に1度開催されている国際現代美術展「岡山芸術交流」。「青豆の公園」(The Parks of Aomame)をテーマに、「岡山芸術交流 2025」が開幕を迎えた。

2016年のスタート以来、岡山市中心部の岡山城・岡山後楽園周辺エリアで3年に一度開催されている国際現代美術展「岡山芸術交流」。その4回目となる「岡山芸術交流2025」(9月26日~11月24日、52日間)が幕を開けた。総合プロデューサーは石川康晴、総合ディレクターは那須太郎。
国際的に活躍しているアーティストたちがアーティスティック・ディレクター(AD)を務めることが大きな特徴となっている岡山芸術交流。過去3回のADを務めたリアム・ギリック、ピエール・ユイグ、リクリット・ティラヴァーニャに続き、今年はパリを拠点に国際的に活動するフィリップ・パレーノがその役割を担う。
今回、パレーノが設定したタイトルは「青豆の公園」(The Parks of Aomame)。村上春樹の長編小説『1Q84』に登場する主人公「青豆」に触発されたもので、同作のストーリーのように、非日常と日常がシームレスにつながるような構成が目指された。テーマが異なる会場(公園)ごとに多様な作品が展開されており、公園のようにすべてが無料で体験できる。
パレーノは開幕に際し、「小説のなかで現実世界と精神世界をナビゲートする青豆のように、市民の方々には2つの世界の間を漂流し、自由に楽しんでもらいたい」と語っている。