訓練めいたデモンストレーションの先に。
佐原しおり評 佐藤朋子+関川航平「サークルナレーティング Section #01」〈テーブルにて〉
アーティストの佐藤朋子が、池袋の書店「コ本や honkbooks」との協働によってパフォーマンスシリーズ「サークルナレーティング」をスタート。本シリーズは、ある書店の一角で、声や言葉を扱うパフォーマンスの場を開くための試みだ。第1回は、同じくアーティストの関川航平をゲストに迎え、「テーブルにて」という副題のもと、ひとつのテーブルを起点に佐藤と関川がそれぞれのパフォーマンスを上演した。本作を埼玉県立近代美術館学芸員の佐原しおりがレビューする。
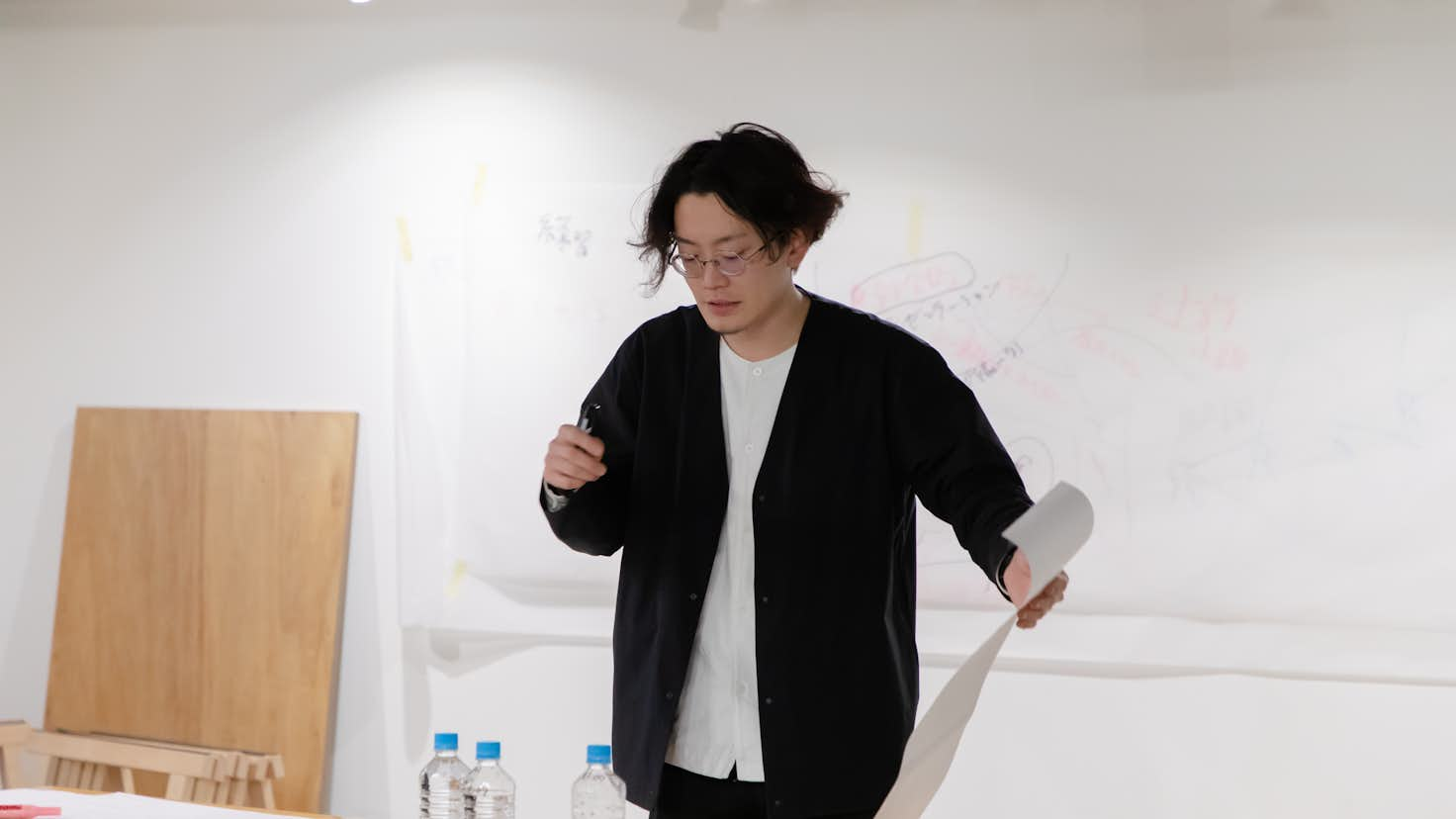
なにか、サラウンドな
日常のなかで経験する「現実」を抽出し、いかに鮮やかに提示することができるか。純粋な「現実」(もしそれが存在するならば)を生け捕りにする試みは、現代美術において主要なテーマのひとつでもある。例えば「もの派」を代表する作家として知られる関根伸夫は、1970年の『美術手帖』に掲載された座談会「特集=発言する新人たち 〈もの〉がひらく新しい世界」において、次のように述べている。
たとえばコップならコップというものの概念性とか名詞性というほこりをはらうということだな。そのとき、 もの ・・は もの ・・になるわけよね。そういうことによってのみ、見えないものが見えるようになるんですよ。あるいは、存在者を存在そのものの方向に解き明かすことでもある。(*)
この座談会から半世紀が過ぎた現在、その頃とは社会も大きく変化し、知覚のあり方や言語そのものも変わってきているように思える。アーティストの佐藤朋子と「コ本や honkbooks」の共同企画によって始まった「サークル・ナレーティング」は、言葉や声に焦点を当てた企画であり、その関心の範疇は「名詞性というほこり」を払おうとした関根のものとは対照的である。しかしながら「サークル・ナレーティング section#01」のゲストとして招かれた関川航平のレクチャーパフォーマンスと、関根伸夫の言葉に代表されるような70年前後の思潮との間には、日常に横たわる現実と知覚のもつれあいの解決を希求するような共通の問題認識があるのではないか。


例えば、パフォーマンスのなかで関川は「見るともなく見ていた」風景の話をしている。2019年の夏、台風が来る2日ぐらい前のこと。鴨川の土手に座った関川が「凧揚げ名人おじさん」ふたりがそれぞれひとつずつ揚げている凧を「見るともなく見ていた」ら、凧のそばを鳥が飛んでいった。そのとき、ちょうど関川の近くにベビーカーを押した若夫婦がやってきて「凧あんで、もう1個凧ある、鳥おる」と言い、その声が関川の耳に届いたのだという。
いま、スマートフォンを右手に握り、親指でスクロールしながらタイムラインを眺めているとしよう。このような日常のある瞬間を抽出しようとすればするほど情報は細分化され、知覚を研ぎ澄まそうとすればするほど、もとにあった感覚は遠のいて、代わりにいくぶん神経質な「現実らしきもの」が立ちあがってしまう。目の前の現実を主観的に切り取ろうとするとき、そこには必ず誇張や省略、逸脱が伴ってしまうことについて、関川は次のように語る。「風景を描写する、図示しようとする、しゃべろうとすることにはつねに歯痒さが伴う」。ふたつの凧と鳥、そして自身の視界が空でひとつに交わるタイムラインを逐次的に描写した若夫婦の声が関川の耳に不可避的に飛び込んできたことによって、幸いにも関川は風景を描写することを免れながら、同時に、過不足なく切り取られた現実を与えられたのである。
他方で、関根伸夫が前述のように「存在者を存在そのもの」にすると言ったとき、存在者(例えば、コップ)の周囲の情景やそれに伴う記憶などの要素は削ぎ落とされている。この場合、知覚する主体が社会的に構築された情報や言語を介さずに存在者と「出会う」ことができれば、そこで目標達成となるのである。「もの派」をめぐる言説において「事物」という言葉が頻出するのは、存在者(コップ)≒「あるがままの世界」として措定されているからではないだろうか。「存在者を存在そのもの」として捕獲することの困難さは、関根、関川両氏が共有する課題である。しかし、関川の関心はより複合的な世界の把握にあり、そこには、それを知覚する人間の身体そのもののポテンシャルに対する洞察を読み取ることができる。

2019年12月28日に3回行われた「サークル・ナレーティング section#01」において、関川は1回の公演ごとに500mlのペットボトルの水を1本飲み、バナナを1本食べることにしていた。会場のテーブルには紙が広げられ、ペットボトルやバナナ、ペンなどが無造作に置かれている。不意にバナナの皮を床に投げ、次に手に持ったペットボトルを指差した関川は、早口でこう言った。
ペットボトルペットボトルペットボトル! 投げたバナナ投げたバナナ投げたバナナ!
「投げたバナナ」と言われたとき、観客はどうしても床に落ちたバナナを見ようとしてしまうのだが、関川はペットボトルを指差し続けてペットボトルに視線を固定するよう促す。このとき、観客の眼はペットボトルを見つめつつ、見ることのできない「投げたバナナ」を「感じる」ことになる。どこか訓練めいた関川のデモンストレーションを通して、人間が何かを知覚するときに必ずしも五感のみが機能するわけではないことを感得させられるのである。たとえバナナの皮が視界に入らなかったとしても、床に投げられたバナナの皮を見た記憶によって、私たちの認知は大きく変化する。

人間は外界の存在と一対一で対峙しているのではなく、つねになにかに取り囲まれ、複雑かつ偶発的な関係を取り結んでいるに過ぎない。19年の夏、関川は壁面にスコアのように言葉を書きつけた作品《散歩られ》(京都芸術センター)を発表している。「サークル・ナレーティング section#01」の最後には、同作をもとにした声によるパフォーマンスが行われた。
…シロツメクサシロツメクサシロツメクサシロツメクサシロツメクサシロツメクサシロツメクサ、が広がってる。シロツメクサ、シロツメクサシロツメクサシロツメクサシロツメクサシロツメクサシロツメクサ。河原から帰ったら、思い出せたりする。
「一面のシロツメクサが広がっていた」とは、とても言えない。風景を認知する主体が思考に追い抜かれたり、また追い抜いたりするようなギリギリの速さで、関川は「シロツメクサ」を繰り返すのであった。
*ーー小清水漸、関根伸夫、菅木志雄、成田克彦、吉田克朗、李禹煥(座談会)「特集=発言する新人たち 座談会〈もの〉がひらく新しい世界」『美術手帖』1970年2月号、p.40




