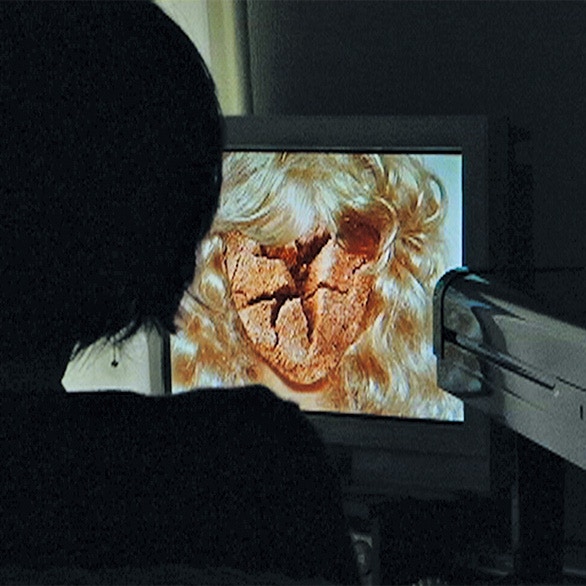コマの人 清水穣評「像の旅 伊藤高志映像実験室」展
福岡にある田川市美術館で開催された「像の旅 伊藤高志映像実験室」展を美術評論家・清水穣がレビューする。伊藤高志のコマ撮り実験映像から読み解く、伊藤が追求した芸術の核とは?

コマの人
21世紀に入って、英語圏の日本写真・映画研究はポスト・コロニアルな新局面を迎え、十分な日本語力と取材能力を備えた研究者による、1950年代から70年代にかけての歴史研究が進んだ。その成果のひとつが、2012年にテート・モダンで開催された森山大道とウィリアム・クラインの二人展であったし、その後も1960年代の日本の批評空間への関心は衰えることなく、ユリコ・フルハタの『Cinema of Actuality : Japanese Avant-Garde Filmmaking in the Season of Image Politics』(Duke University Press、2013)、スイスのヴィンタートゥーア美術館(2016)やスペインのバレンシア(Bombas Gens Centre d’Arts Digitals、2019〜20)でのプロヴォーク関係の展覧会が、その背景をなしていた足立正生、松本俊夫、松田政男といった同時代の論客に光を当てて、中平卓馬や多木浩二の言説を相対化していった。
松本俊夫は、伊藤高志の師にあたる作家である。彼の『映像の発見 アヴァンギャルドとドキュメンタリー』(三一書房、1963/清流出版、2005/ちくま学芸文庫、2024)に収められた映像批判には、のちの中平卓馬のメディア批判や松田政男の風景批判が(言葉遣いまで含めて)先取りされている。彼らの批判の要諦は、すべてを破綻のない物語と連続的な映像の流れ(=「風景」)に取り込んで、戦後日本社会の抑圧に貢献する、一般メディアの映像文化に抗して、いかにしてそこに亀裂を走らせ、歴史の断絶を復活させるかということで、伊藤高志のコマ撮り実験映像は、当然ながら、それに対する1980年代からの応答であるだろう。


本展は、作家本人がその40年以上にわたる創作を振り返った回顧展ではなく、以上のような文脈を踏まえて、澤隆志・藤本亜季の両キュレーターが企画し、システム設計を八嶋有司、インストールを坂㟢隆一が担当してできあがった、つまり、2025年の現在から他人が振り返った回顧展であり、それが本展に過不足のないキレの良さを与えている。正面の第1室で大型スクリーンに投影される作品は、1981年の《SPACY》、1995年の《ZONE》、2010年の《甘い生活》の3作に厳選され、作風の変化(あるいは無変化)を追うことができる(ただ、《甘い生活》で音声が背後から聞こえたのは、プロジェクターの都合か、そういう意図だったのか)。右側の第2室では、作家のルーツである小学生時代の漫画作品(手塚治虫や横山光輝の絵柄に影響されたSF怪獣作品で、子供が考えたとは思えないコマ割り!)に始まり、《SPACY》以降のコマ撮り実験映像作品(《BOX 》《DRILL》《GRIM》《WALL》など)の技法、撮影装置や設計図、絵コンテ、さらに映像を構成する写真を展示することで、伊藤高志の才能の核の部分を、いわばむき出しにして解説している。ここがもっとも見ごたえのある部屋であったし、伊藤作品が観客に差し向けるすべての謎の答えはここにあるだろう。左側の第3室は、《SPACY》を題材として、第1室とは対照的に、つまり約40年前の制作にかかったあの苦労を現代の技術で過去の遺物となし、スマートフォンによるコマ撮りとそれを編集するソフトウェアを用いて、オリジナルよりもきれいな映像でつくり直してみましょうという、他人による回顧展ならではの、ユーモラスな実技コーナーで、それは、作家の出世作が、畢竟、映像の自己言及的な繰り込み(マグリットの《複製禁止》[1937]以来の?)という方法論に尽きてしまうのか否か、という厳しい問いかけでもある。最後に、3つの部屋から少し離れた小映写室では、第1室と第2室に登場した作品群のあいだを埋めるかのように、その他の伊藤作品が上映されていた。


さて、キュビスムとは、空間的に見れば、ある対象を様々なアングルから撮影した矩形のイメージ(レイヤー)のコラージュであり、時間的に見れば(デュシャンの《階段を降りるヌードNo . 2》[1912])、ある運動を始めから終わりまで撮影したショット(レイヤー)のコラージュと見なせるだろう。どちらもひとつの視点、ひとつの瞬間を拡張しようと、その「ひとつ」のなかに「多く」の視点や瞬間を繰り込む技法である。ハンス・リヒターの《Rhythmus21》(1921)にさかのぼる、コマ撮りによる実験映像がその直系であることは言うまでもない。
1つの線分を3等分し、2つの分割点を頂点とした正三角形をつくる(左右に裾野を持った正三角形の山型)。この最初の山型の4つの辺を、それぞれ同じ山型で置き換えてできるイガイガ図形の16個の辺をさらに同じ山型で置き換えて出来る図形の64個の辺を同じ山型で置き換え……この自己言及的な繰り込み操作を無限に続けると、コッホ曲線というフラクタル図形ができあがる。自己繰り込みの効果は、曲線の次元が1次元をはみ出す(1・26次元)ことと、連続しているのに微分不可能になることである。後者は、連続性の概念を大きく変えさせる。連続性とは、なめらかに切れ目なくつながることではなく、無限の分割可能性(接点がありえないので微分不可能)なのだ。ここで静止画を1次元(次元数は任意)、動画を2次元とすれば、コマ撮り映像は、その中間的な分数次元を持つだろう。つまり、伊藤高志の芸術の核とは、1枚の写真を無限のコマに分割することで、通常次元からはみ出させることなのである。

他方で、伊藤高志の映画作品が観客のなかに呼び起こす疑問のひとつが、1990年代から顕著化するそのホラー趣味であると言って異論のある人は少ないだろう。しかもなぜか、そのホラー趣味は、かなり既視感の強い(長い黒髪の女、喪服)、しかも意図的にチープな(金髪のウィッグ)もので、さらに撮影方法ともどもかなり古臭い(古い映写機、女たちのメイク、ファッション、目や唇のショット、頻繁に挿入される雲のショット)。疑問の2つ目は、このレトロ趣味に関わっている。《甘い生活》が2010年制作と知って驚かない人がいるだろうか。映像の質はまるで1960年代の映画のようであるし、電子的な効果音も、時代が判らない撮影場所(昭和の被差別部落に特徴的な団地や郊外のゴミ処理場など)も、実相寺昭雄監督の『ウルトラセブン』に登場するメトロン星人の長屋を思わせ、女たちはといえば変装した宇宙人である。ホラーもレトロも、昭和映画のアプロプリエーションと見なすには真面目にすぎるし、好んで挿入される「前衛舞踏」も現在ではすでに歴史の一部、鄙びた踊りにすぎない。じつは、師の松本俊夫による『薔薇の葬列』(1969)にも、つくり物をつくり物としてチープに演出してそれを隠さない感覚(ピーターの滑稽な美しさ=醜さをそのまま放置する)があるので、それへのオマージュなのかもしれない。
ただ重要なことは、上に述べた「はみ出し」は、自己繰り込み(無限分割)によって生じるものであり、何かを付加することで生まれるものではないことである。なるほど写真は、霊視、念写、場所の記憶……等々、人間の目を超える、「見えない何か」を現像するメディウムとされてきた。心霊写真、ホラー写真に見られる、激しいブレやアレ、二重露光はその通俗的な表現である。結局のところ、普通の実写撮影では、レトロで既視感のあるホラー趣味が作品に時代遅れの閉塞感を付加しており、逆に、本来人工の極致であるはずのコマ撮り場面でこそ、画面は息を吹き返すのだった。
福岡県田川市と聞いてピンとこなくとも、山本作兵衛による筑豊炭田の記録画・記録文書がユネスコ世界記憶遺産になった(2011)ことは広く知られているだろう。炭田の閉鎖は行く当てのない大量の失業者を残し、田川市は福岡県(生活保護受給率全国4位)のなかでも受給率が高いことで知られている。とはいえ、見るべきもののない街かと思いきや、西日本でよく知られる菓子「チロルチョコ」のルーツ(松尾商店)は田川市にあり、頂上から削り取られて台形状になってしまった香春岳(かわらだけ)の奇景がセメント産業の存在を誇示しており、そしていま、伊藤高志の回顧展が開かれている。かつて富山県砺波市の美術館が東松照明のカラー写真に焦点を当てる優れた小回顧展を開催して驚かされたことがあったが、今回の驚きはそれ以上であった。予算規模も小さく観客動員数の望めない地方美術館が、量より質で勝負するその熱意と努力は、どれほど評価してもしすぎることはない。
(『美術手帖』2025年7月号、「REVIEW」より)