シリーズ:これからの美術館を考える(8)
コレクション/キュレーション/鑑賞の関係を再構築しよう
5月下旬に政府案として報道された「リーディング・ミュージアム(先進美術館)」構想を発端に、いま、美術館のあり方をめぐる議論が活発化している。そこで美術手帖では、「これからの日本の美術館はどうあるべきか?」をテーマに、様々な視点から美術館の可能性を探る。第8回は、和歌山県立近代美術館教育普及課学芸員・青木加苗が美術館におけるコレクション、キューレション、そして鑑賞の関係を再考する。

(663highland, CC BY-SA 3.0
「これからの美術館」は制度によってつくられるのではない
筆者はこのシリーズ「これからの美術館を考える」を、一読者として眺めていた。「眺めて」と思わず書いてしまったところには、筆者と各執筆者の主張との心の距離が表れている。それぞれの議論が美術館と学芸員の制度的な面への問題提起で、心の中で首肯・反論するところはあるものの、自分には何をどうできるわけでもなく、人口減少が加速し予算逼迫に悩む地方の美術館に勤める名もない、一学芸員の耳にはどうにも遠い雲の上の話に聞こえてならなかったからだ。
いや、他人事だと言いたいわけではない。筆者は昨年5月に全国美術館会議が公表した「美術館の原則と美術館関係者の行動指針」の策定に末席ながら携わっていたし、日本の美術館がどうあるべきか、少ない経験のなかでも真摯に考え続けてきたつもりである。ただそれは、ひとりの学芸員としていま何をすべきか、明日自分に何ができるか、というささやかなもので、誰かに影響を及ぼすような大それたものではない。しかしこういった現場の学芸員たちの日々の仕事こそが、いや、学芸員だけでなく総務部門や受付・監視職員、設備担当も含めたあらゆる美術館人たちの仕事が、「これからの美術館」の姿をかたちづくっていくのではなかろうか。そうでなければならないし、私たち一人ひとりがその責任を負っているという自覚を持つべきでもある。さもなければ、制度がどう変わろうとも、この国の美術館の本質は変わらない。
おそらく「これからの美術館」をより良いものにするために必要なのは、現状を一気に打開する「スペシャルなアイデア」を誰かが出してくれるのを待つことではない。規模の大きな一握りの「主導的な(リーディング)」美術館をモデルに議論がなされるのを、遠巻きに見ていることでもない。館の規模や仕事の大小にかかわらず、美術館に携わる私たち一人ひとりが、日々の仕事に直接関わるところから考え、改善策を試行錯誤し、気付きと知恵を共有して、議論を深めていくことから始めるしかないのだ。そのための試みとして筆者は、展覧会も教育普及も担当する学芸員として、常に思いを巡らせてきたコレクション、キュレーション、そして鑑賞という三つのキーワードに基づいて本稿を記すことにした。
コレクションと公共性
「リーディング・ミュージアム(先進美術館)」の問題から話を始めよう。この構想が多くの反発を引き起こしたのは、美術館活動の根幹のひとつである作品収集(収蔵)を、その価値付けのために意図的に行わせようという魂胆が見えるからだ。そして一度収蔵された作品を動かすことで市場価値を高めることができ、それが美術市場の「活性化」であると考えているところにも、異論が噴出した。この構想の危うさについては筆者が繰り返すまでもないが、その根底にあるのは、美術館のコレクションについての無理解ではないか。
では美術館のコレクションとはなにか、作品収蔵がどのようなプロセスをたどって行われるのか、関係者には釈迦に説法だが、一般にはあまり知られていないだろうから、簡単に振り返っておきたい。
国公立館の場合、まずは各館が収集方針を定めている。地域性や軸となる作家、事象が記されたもので、それにそぐわないものは原則、収集対象とならない。この収集方針は近年ウェブサイトで公開している館も増えており、そうでなければ毎年の事業を報告する年報等に載せられているので、比較的容易にアクセスできるだろう。学芸員は自館のコレクションを豊かにするために情報収集をする。そして「これは」というものを館内協議に上げ、選定委員会や収集委員会といった名称の有識者による第三者委員会に諮ることを決める。これは年に1、2回しか開かれない。審議にかけるためには作品現物を持ってこなければならないが、場合によってはその輸送費を自前で捻出する必要があるため、すぐに作品を動かせるとは限らない。
そしてこれらの段階を経て、無事に委員会にかけられるとなれば、担当学芸員はその作品が自館にとってどのような意味を持つものか説明するための資料を作成する。そこには評価額や他館での収蔵実績なども含まれる。こうして委員会による審議・了承を経て、公立の場合はさらにその後、役所の決裁・支払いが行われて、ようやく晴れて収蔵となる。収集の方法は購入に限らず、受贈、管理替え等があるが、いずれにしても同じプロセスを経なければ収蔵できない。つまり、いくつものハードルがあるのだ。
収集活動がこういった細かな手順を必要とするのは、美術館が所蔵する作品が公共の財産となるからである。ここで言う「公共」という語の指すところは、一般には税金で買うことによって生じる属性だと考えられているかもしれないが、本来もっと広い意味でとらえる必要がある。つまり、収蔵によって作品や資料を未来へつないでいく活動自体が社会から美術館に託された責務なのであり、その仕事が有する公共性、あるいは公益性によって美術館という存在が担保されているということだ。よって、収蔵作品が公共の財産であることは、国立、公立、私立といった設置者の区別とは関係がない。こういった考え方は、ICOMの倫理規定をはじめ、ミュージアム論の前提であるが(*1)、残念ながら日本には未だ根付いていないために、「リーディング・ミュージアム」という構想が出てきたのであろう。しかしたとえ時間がかかろうとも、ミュージアムについての共通理解となるよう広めていくほかはない。
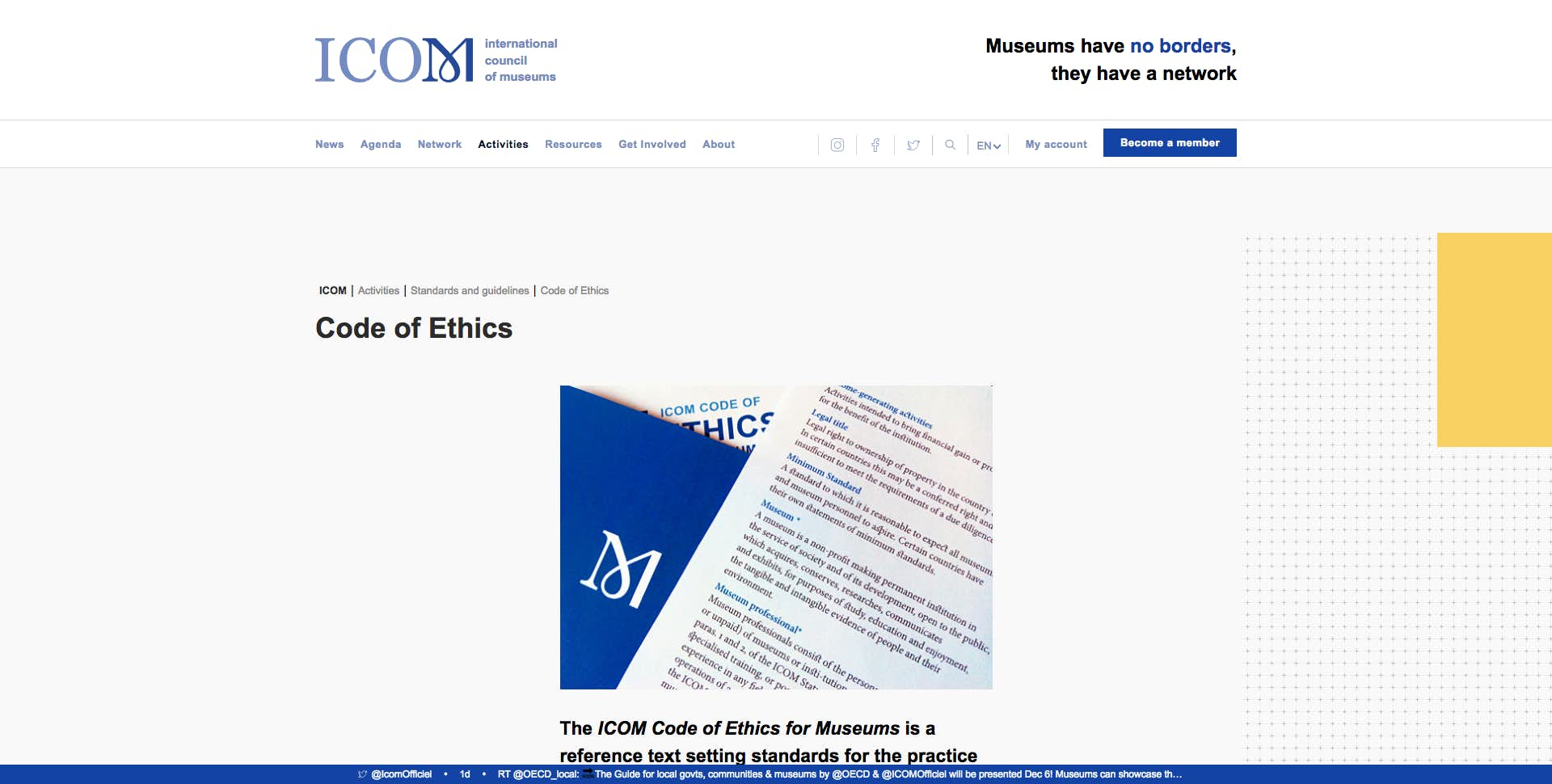
コレクションというキュレーション
このような収蔵のプロセスは、ときに長い時間と手間、そして所蔵者・関係者との深い信頼関係を必要とする。しかし多くの学芸員はその苦労を厭わず、むしろ喜びと感じて励んでいるだろう。限られた予算と時間、人手ではあるが、自館の未来にとって有益な作品をひとつでも多く集めることに、仕事の意味を見いだしているからだ。ただし最近ではほとんどの公立館で購入予算が削減され、ゼロになっているところも少なくないため、収集の仕事が引き継がれにくくなっていることは大きな問題でもある。
しかし良い収集とは、ただ高値がついている作品を買い集めることではない。地道な美術館活動に理解を示すコレクターから貴重な作品が寄贈されることもあるし、全国的にはあまり知られていない作家であっても、各地域の美術の動きを示すためには貴重な資料となることもある。必要なのは、自館のコレクションに何を付け加えるべきか考え、常にアンテナを張っていることだ。
このように多面的に行われる収集は、日々の活動と密接に関わり、美術館を成長させることにつながっていく。そしてもっとも大きなファクターとなるのは、やはり展覧会という社会との直接的な接点である。例えば近代以前の美術を扱っていると、展覧会を見た来館者から作品の情報が寄せられることもあるし、展覧会のための調査を通して、ある作家の遺品の中から思いがけない関連作家の作品が見つかることもある。現代作家の作品であれば、自館で開催した展覧会での新作を収集することが、もっとも直接的な意味を持つはずだ。展覧会の歴史が美術館の歴史となり、それがコレクションの蓄積となっていく。このサイクルが、コレクションを持たずに出発した日本の美術館の目指すべきかたちではなかろうか。
そしてコレクションにどんな作品を加えるかを考えそれを実現することは、ひとつのキュレーション行為である。だから私たち学芸員は、展覧会をキュレーションする前に、コレクションというキュレーションを行っていることに、いま一度意識を向ける必要がある。このことに目を向ければ常設展示、さらにはコレクションを用いた企画展の意味は変わってくるはずだ。それは過去、現在、未来の学芸員たちが協働して行う、最大規模のキュレーションと呼べるのであるから。そして収集予算がないことが、学芸員の能力向上に停滞を招いていることは確かだろう。予算のある国立館や一部の館と収集に目を向けられない館との間には、コレクション形成に対する大きな意識の差が生まれている。
コレクションの価値は理解されているか
しかしこうした収集活動が、美術館の外部にどう受け止められているかは別の話である。公立美術館の場合、作品収集の財源は直接的な税金となるため、「血税の無駄遣いではないか」という声がたびたび聞こえてくる。それは議会での質疑であったり、来館者からの直接の意見であったりとさまざまであるが、公立館の学芸員なら皆、一度は経験があるだろう。国立館の作品収集ももちろん税金によってなされるが、個人と国の距離感は、県民、市民と公立館のそれとはまったく異なっている。筆者の経験から言うと、日本の公立美術館が数多く所有している戦後アメリカの大型美術作品は、美術館の設立時に高額で購入されていることもあり、槍玉に挙げられがちである。そして必ずと言っていいほど、「よくわからない作品に◯億円」「子供でも描ける」といった、作品が理解できない不満と結びついた批判が聞こえてくるのである。
このような意見を持つ相手に対し、それがいかにその館にとって意味のある作品かを理解してもらうことは容易ではない。価値判断は、価格によってしか行われないからだ。それはいくらまでなら妥当で、いくら以上なら無駄遣いなのか、という議論ではない。自分たちの理解できないものを、税金を使って購入すること自体が無駄と受け止められているのだから。あるいは「高価だからありがたがる」という逆転現象も起こるのだが、根っこは同じである。
「リーディング・ミュージアム」構想で想定されている作品の価値も、同じく作品の値段を指す。美術館活動が作品の市場価格に少なからず影響を与えることは当然で、作家の個展が美術館で開かれれば、近くの画廊で関連する展示が行われ、作品が市場に出てくる。このこと自体は問題ではないし、古い時代を扱っていれば新たな資料の発見が促されるメリットさえある。しかし「作品の価値=作品の値段」として疑わないことは収集活動において大いに問題であり、加えてその価値付けをするのが美術館(学芸員)と批評家の専売特許であると考えていることもまた、大きな誤解ではなかろうか。これについては後述したい。
作品を手放す方法を日本の美術館は持ちうるか
ただ、この「構想」のおかげで、これまであまり意識されていなかった問題が露わにもなった。それは日本の美術館には、コレクションを手放す術がおよそないという事実である。国公立館が作品や資料を収蔵するにあたっては、この先もそれらをずっと守り続けていくという認識に立っている。これは先述の「コレクションは公共財産である」という考え方と齟齬を来さない。
いっぽうで公益財団法人格を有する私立美術館の場合は、コレクションの売却は理事会の承認を必要とする旨が定款に記されている。そして公益財団法人格を持たない私立(私設)美術館の場合は、私有財産であるために売却される可能性を大いに孕んでいる。記憶に新しいところでは、DIC川村記念美術館が所蔵していたバーネット・ニューマンの作品や日本画コレクションの放出が、この例に当てはまるはずだ。ともに公共性に依って立つ仕事をしているはずの美術館でありながら、設置者の区別によってコレクションの扱いが異なっている。
結論から言えば、問題は国公私立を問わず美術館が、作品を手放す場合についてほぼ想定していないことにある。日本の美術館の歴史を考えればわかることだが、戦後、とくに70年代以降、各自治体が美術館という箱をこぞってつくった。ほとんどの場合、欧米の美術館のようにまとまったコレクションがもとになって設立されたわけではなかったため、空っぽの収蔵庫を埋めることが先決であった。集めることには躍起になったが、手放すことを考える機会はなかったというわけだ。
諸外国はどうだろうか。じつは欧米の多くの美術館では、どのように作品を扱うかの方針を明文化しており、これはコレクション・マネジメント・ポリシーと呼ばれる。収集した作品をどう管理するか、つまり収蔵品のデータベース管理と収蔵庫内にある作品へのアクセスを含めた実体あるモノの管理方法、つまりレジストレーションが第一の課題となる。そこには、昨今日本でもようやく目を向けられ始めたアーカイヴの方法論や、作品貸出しの方針、保存環境、安全対策といったトータルの視点も盛り込まれる。先に保坂健二朗氏が雑芸員とも揶揄される日本の学芸職を解体し、キュレーターとレジストラーの仕事を区別する案を説かれたが、それを本気で実現するためには、まず前提となるコレクション・マネジメント・ポリシーをつくる議論が必要だろう。方針なき管理はただの倉庫番であるし、担当者変更による問題も生じかねない。(*2)
そしてこのポリシーの中には、コレクションをどう処分するかについても記されている。膨大なコレクションを持つ欧米の美術館では、コレクションの大半が展示されないからだ(ちなみに日本で開催される海外の美術館コレクション展は、自館ではあまり日の目を見ることのない作品を集め、そこに名の知れた作家によるいくつかの目玉作品を組み合わせたもの、というのが少なくない。これを揶揄して「虫干し展覧会」という表現もある)。
その結果、限られた収蔵スペースを喰い、管理にもお金はかかるため、公開できないコレクションに意味はあるのかという議論が、最近盛んに行われているのである。昨年、ICOMにある美術の国際委員会ICFAの年次大会でも、「常設展示とその収蔵」が会合のテーマに据えられたが、そこでの基調講演は、オランダのボイマンス・ヴァン・ベーニンゲン美術館館長による同館の新たな収蔵庫の話題であった。これは来館者が中に入ってガラス越しに作品を見られるもので、展示室では見せられないコレクションを公開する新たな術として、昨今目立ってきたアイデアである。リニューアル準備中の宮城県美術館も、同様のコンセプトに基づく新たな収蔵庫を計画中であると聞く。今後、美術館の収蔵庫についての考え方は、世界的にもこの方向で進んでいくだろう。

それでも収蔵スペースには限界があり、将来にわたって継続したコレクションの成長を考えるなら、私たちもコレクションの処分について検討を始めることが必要だ。コレクション・マネジメント・ポリシーを支える考え方としてはICOMの倫理規定に「収蔵品の除去」という項目があるが、ここには、ミュージアムがコレクションを処分するのは別の作品・資料を購入の場合にのみ許されることが明記されている(*3)。運営資金を補填するためにコレクションを放出することは、あってはならないのである。
実際に今年、アメリカの美術館が運営資金調達のためにコレクションを手放したことが報じられたが、AAMD(美術館長協会:Association of Art Museum Directors)はこれらの美術館に作品の貸借を禁じる制裁を科した。このニュースを見て、アメリカの美術館の自律性と、コレクションの公共性、公益性が十分に理解された社会の成熟に、筆者は感心し、うらやましさを覚えた。今の日本の美術館が作品を処分する方法を安易に設ければ、間違いなく管理運営費の補填に高額な作品を売却せよという意見が出てくるだろう。ICOMの倫理規定や全国美術館会議の「美術館の原則と美術館関係者の行動指針」があっても、「リーディング・ミュージアム」構想が出てくる現実を思えば、それが守られる素地はこの国にまだ育っていない。

(Berkshiremuseum, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons)



