バンクシーのネズミはなぜ傘をさしているのか? ストリートの現実主義とファンタジー
2019年1月に東京・日の出で発見され、都が撤去した「バンクシー作品らしきネズミの絵」。本作の議論のひとつが、バンクシーのものかという作品の真贋。また、バンクシー本人によるものだと判明した場合にも、作品を一般公開することは公共物に描かれた「落書き」を都が認めることになり、ダブルスタンダードではないかという批判も出ている。また、バンクシーの手法を真似た作品も日本各地に出現するなか、「この騒動すべてがバンクシーの作品と呼べるのではないか」という指摘もある。バンクシーに直接インタビューをした経験を持ち、バンクシーに関する本の翻訳を多く手がけてきた鈴木沓子は、一連の騒動をどう見ているのか。作品の意味を解説する。

バンクシーがその活動初期から描いているキャラクターで、もっとも登場頻度の高いモチーフが、今回、東京・日の出駅近くの防潮扉で見つかったラット(ネズミ)のステンシル画だ。現在、この作品に関しては本物か否か、真贋をめぐる議論がさかんだが、筆者は本物だと考えている。もちろんバンクシーは匿名で活動する特殊なアーティストなので、都庁側の対処によってはバンクシーが公式に作品を否定する可能性も残っている。
しかし、バンクシーのウェブサイト、また作品集『Wall and Piece』や本人が監督した 映画『イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ』にも作品画像が登場することや、来日当時の証言など、バンクシーによるものと認めざるをえないような状況証拠が多すぎる。公式媒体に繰り返し登場していることを見ると、本人が気に入っている作品である可能性も高い。ただ「何がアートで、何がアート作品じゃないかは鑑賞者が決めること」というのがバンクシーのスタンスだ。
美術界では、作品の真正や価値を決めるのは、「どこの誰が描いて、どんな人が作品にお墨付きを与えたか」という来歴が重要視されるが、それよりも「作品自体が“何をどう表現しているのか”で評価されるべき」という考えもあって、バンクシーは匿名で活動している。
その彼の信義に倣って、ここでは現在、都庁で“公開”されている作品がどんな作品なのか、また「アンブレラ・ラット」(傘を持つドブネズミ)という、バンクシーの作家性をよく表しているシリーズであったことについて、その意味を考えてみたい。
イギリスのパブリック・エネミー“ドブネズミ”
バンクシーは、イギリスのブリストルで活動を始めた1990 年代当初は、フリーハンドのグラフィティを描き、アルファベットで「BANKSY」とボムする(グラフィティを書きなぐる)タギングも残していた。しかしその後、ロンドンに移ってからは、ラットのステンシル画を大量に描き始めるようになる。
ここで大事なのは、イギリスでラットと言えば、日本でのハツカネズミ(マウス)ではなくドブネズミを意味するという点だ。都知事は防潮扉の絵を指して、「かわいいネズミちゃん」とほほ笑んだが、バンクシーの描くラットは病原菌をまき散らしたり、家財や電線を食いちぎる害獣として忌み嫌われているものだ。イギリスの首相官邸では300年前から政府公認のネズミ捕獲長であるネコが代々飼われているほど、ラットはまさに“パブリック・エネミー(社会の敵)”であり、そこが作品のカギになる。

バンクシーは、働けど働けど生活はラクにならない労働者階級である自分を、回し車の中でくるくると回り続けるラットレースのネズミに見出したのか、もしくは人目を盗んでグラフィティを描き続ける自分自身をドブネズミに重ね合わせたのか、イギリスだけでなく世界のあちこちにラットを描き残している。傘で空を飛ぶラット、カセットデッキを持つBボーイ風のラット、壁に落書きをするラット、カメラを手にしたラット……。昨年6月にはパリ・エッフェル塔の近くで、観光をするような2匹のラットや覆面でカッターナイフを手にするラットも発見された。

本人名義で自費出版したジンの中でバンクシーはこんな記述をしている。「普通の人と同じように、俺にもファンタジーがある。それは取るに足らないと思われている者たちが、ある日、地上に出てきて反乱を起こすことだ」。
「反乱を起こす」=「反体制」と思う人もいるかもしれない。実際にここ3ヶ月あちこちで「バンクシーは“反体制”なのに、都知事が作品と記念写真なんて……」というつぶやきを見聞きした。しかし「バンクシーは反体制・反権力の作家」という理解にとどめると、本質を見失ってしまう。

たしかにバンクシーは、グラフィティ・アートという違法行為を手法に、これまで反金融資本主義、反グローバリズム、アンチ五輪、環境問題を提起するようなメッセージ性の高い作品を発表してきた。その規模も年々巨大化して、ディズニーランドを揶揄したアートのテーマパーク「ディズマランド」をつくったり、イスラエルによるパレスチナ人の迫害を訴えるため、分離壁沿いに“世界一眺めの悪いホテル”の「ザ・ウォールド・オフ・ホテル」をオープンしたり、オークションに出品された自身の絵をシュレッダーにかけてみせるなど、インパクトある作品が続いたこともあって、子供心やファンタジーを重んじる作家性は影に隠れてしまったように感じる。

例えば、パレスチナの壁に描いた代表作では、マスクで覆面をした過激派の男性に投石の代わりに花束を投げさせたように、バンクシーは無許可で作品をボムするという手法は乱暴に見えたとしても、そのメッセージは決して暴力的な攻撃ではなく、ファンタジーや美学であることの方が多い。そして心情は反体制側に寄り添っても、そこに拠って立たない精神を持ち続ける。教条的で直接的なスローガンは避け、その代わりに目を引くステンシル画やユーモア、あっと驚かせるアイデアで何重にも内包しているからこそ、落書きではなく作品として鑑賞され、街に残ってきた。だからこそ、世界的に有名になれたとも言える。

ストリートに出現した『メアリー・ポピンズ』のオマージュ
防潮扉の作品の話に戻ろう。あのラットはなぜ傘と鞄を手にしているのだろうか。バンクシーの故郷イギリスで、傘と鞄といえば、やはり児童文学『メアリー・ポピンズ』を連想させる。東の風に吹かれて空からやってきたメアリー・ポピンズが魔法を駆使して、子供たちには現実と地続きの異世界を体験させ、仕事と時間に追われて疲れた大人たちには「なんのために生きているのか」を改めて気づかせる。その物語に幼年時代に親しんだ人は多い。
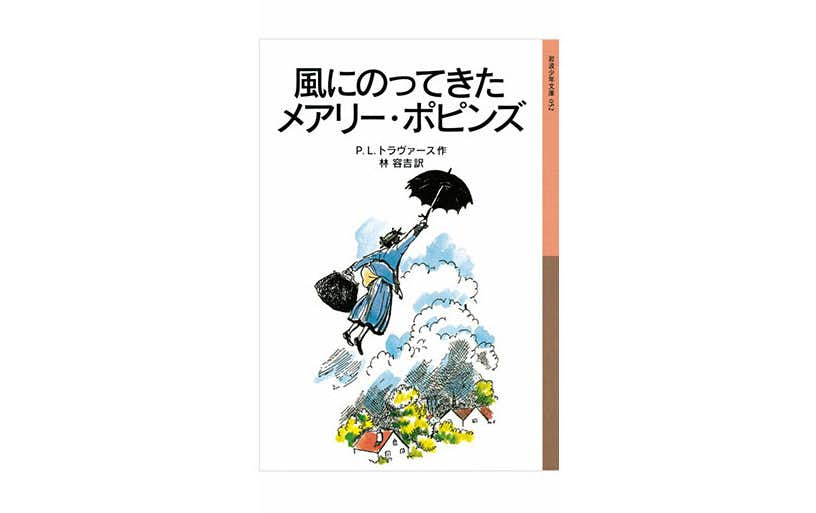
実際、バンクシーの作品集『Wall and Piece』や『BANKSY YOU ARE AN ACCEPTABLE LEVEL OF THREAT』にも、「アンブレラ・ラット(傘を持つラット)」シリーズの作品が掲載されているが、この作品がロンドンの街角に現れたとき、にやりとしたロンドン市民は少なくなかったはずだ。それは日本でいうならば、ドラえもんのタケコプターで空を飛ぶネズミの絵を、街で突然見かけたような郷愁感のある笑いと言えば近いだろうか。
国民的キャラクター「メアリー・ポピンズ」のトレードマークである傘を手に空を飛ぶ、社会の敵であり嫌われ者のラット。そこには「たとえ地上を這う嫌われ者でも、傘を持って空へと高く飛べるはず」というシビックプライドや、「もう空から舞い降りるヒーローやヒロインを待つのではなく、自らの傘で飛べばいい」というメッセージも垣間見られる。
そして、お役所に向けては「あなたたちが街に設置する歴史的な記念碑や銅像や難解な公共芸術より、(アンブレラ・ラットは)よっぽど自分たちの街だと感じられる作品だし、少なくともあなたを楽しい気分にさせませんでしたか?」というささやかで不遜な提案も滲ませている。「メアリー・ポピンズ、覚えていませんか?」と。

バンクシーは防潮扉の日本語の標識を理解していたのか?
奇しくも今回日本で発見された作品は「アンブレラ・ラット」で、それは東京・日の出の小道に設置された防潮扉に描かれていていた。この防潮扉は、通常は人が通行できるように扉は開かれているが、増水時には堤防の役割を発揮する緊急時の防災施設で、そこには赤の太字で「通行止」と書かれている。バンクシーがこの日本語の意味を理解していたのかはわからない。でも「通行止」と書かれた扉の下で、その扉を、傘を手に乗り越えて行こうとするネズミの姿は、パレスチナの分離壁を風船を使って乗り越えていこうとする少女の作品を喚起させる。

このようにバンクシーの作品は、街全体をキャンバスに、周りの風景を借景として「絵」を仕上げるので、絵の部分だけを取り外してしまうと意図がわからなくなってしまうことが多い。よって、描かれた場所に作品が存在することに意味があったのだが、残念ながら今年1月に都庁は絵が描かれた鉄板を防潮扉から取り外してしまったので、このアンブレラ・ラットと防潮扉、周りの風景とが、どのように交じり合って作品が構成されていたのか、いまはもう検証することができない。

捕獲されたラットと脅される“バンクシー劇場”
都庁側からは「バンクシーかもしれない作品を劣化や盗難から守るために取り外した」、「世間の関心が高いので一般公開する」という説明があったが、そもそも作品は作家の意志のもと、あの場所で描かれ、一般に無料で“公開”されていたものだ。欧米ではバンクシー作品が発見されると、その上から透明なアクリル板などを貼って作品を保護し、そのままにしておくケースが多いが、あの場所で期間限定でも公開することがかなわなかったのは残念でならない。ストリートアートはストリートで生きているからだ。
都知事は作品公開時に「バンクシーさん、何か問題があればご連絡ください」とメディアを通じて呼びかけていたが、バンクシー側から連絡がくることはないだろう。日本は他国よりグラフィティに対する取り締まりが厳格であることは、バンクシーだけでなく多くのライターに知られている。仮に自分の作品だと認めれば、今後、罪に問われる可能性もある。そしてバンクシーが無許可で作品をストリートで発表する活動を続ける限り、ここで捕まることはできない。それは、“バンクシーというファンタジー”の終わりだからだ。そしてバンクシー劇場というファンタジーを終わらせたくない、そう願う人たちの想いがバンクシーの活動を20年近くも延命させている。

バンクス氏のままで“バート”に変身したバンクシー
思い出してほしい。メアリー・ポピンズが風に乗って舞い降りた家は、銀行員の厳格な父である「バンクス氏」の一家だったことを。懸命に働いても家族を守ることすらが難しくなった時代に、生真面目なバンクス氏はお金と時間に追われて、心の余裕を失っていた。そしてメアリー・ポピンズは、子供たちのためだけではなく、バンクス氏のように理想と現実のはざまで疲れた大人たちに手をさしのべるためにやってくる。

バンクシーは、アーティストにならなければ、銀行員バンクス氏のような大人になっていたという自覚がどこかにあるのかもしれない。その人生の規定路線から降りて、匿名のアーティストになったことで、閉塞感のある街の路上に無料で絵を描きはじめる。そうすることによって、まるでメアリーの親友・バートのように、子供や疲れた大人を絵の中の世界へといざなう役割を手にし、自分自身がファンタジーのつくり手になった。
バートは「チム・チム・チェリー」を歌いながら煙突を掃除するだけではなく、ときには凧売りをしたり、大道絵描きにもなって、様々な世界を見せてくれる。それは、どんなに不本意な社会や現実にいても、誰でも自分のファンタジーを持って生きていくことができるし、「ファンタジーや想像力をもって現実は変えることができる」という可能性を示唆している。それは、まさに正体不明のまま20年以上も世界的に活躍するバンクシーが体現してきたことにほかならない。
アンブレラ・ラットと防潮扉の行方
しかし都庁の発表によると、じつはこの防潮扉は、いずれにしても撤去される予定にあったという。津波被害を防ぐ防潮扉は全国各地に設置されているが、東日本大震災ではこの防潮扉を閉鎖しにいった作業員が逃げ遅れるという被害が相次いだため、手動で開閉するタイプの防潮扉は今後撤廃されるというのだ。つまりいずれは、このラットも防潮扉と一緒に撤去される運命にあった。それを考えると、作品が防潮扉とともに撤去される前に、東京でこれだけの騒動を巻き起こしたということは作家の本望だったとも考えられる可能性もある。しかし、その答えは、今後、都庁が作品をどう対処するかにかかっている。











