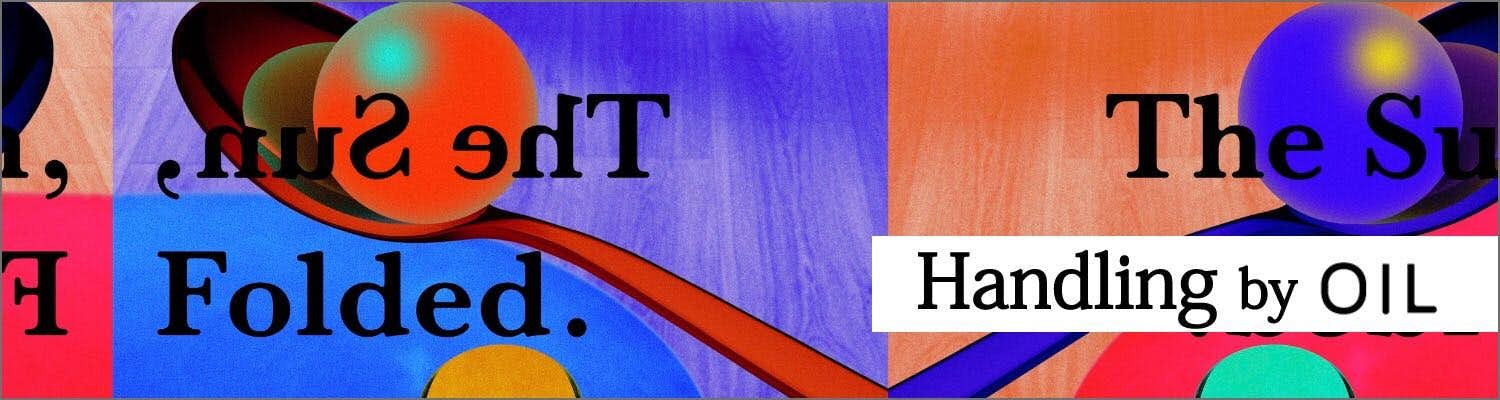リフレクトし、スケールアウトするプラザ。玉山拓郎インタビュー
渋谷パルコにオープンした「OIL by 美術手帖」ギャラリーで、個展「The Sun, Folded.」を開催中の玉山拓郎。これまで日用品などのファウンドオブジェクトを用いた展示や、強烈な色に照らされた空間的作品が注目されてきた玉山が、最新作となる本展では映像を用いたインスタレーションを発表。「いま、自分の使う要素がものすごく整理されている」という作家に、その方法論や現在地を問う。

空間的な絵画行為から、空間的な作品づくりへ
──僕が最初に玉山さんの作品を見たのは、国分寺のswitch pointの個展(「I WANT TO TELL YOU HOW MUCH I LOVE」展、2015)でした。それほど広くはないギャラリー空間に、入れ子となるようなキューブをつくり、そのなかで箱庭の三次元版のような作品を展開していました。箱には茶室のにじり口のような狭い入口があり、腰をかがめて入っていくと、そこにはライティングや物のサイズや配置で重力が揺らぐような、別の世界が広がっていた。一瞬で感覚がずらされるようで、すごく印象に残っています。
その後の、「アッセンブリッジ・ナゴヤ 2016」や武蔵小金井(「Pole Ball’s Landing Life」展、小金井アートスポットシャトー、2017)の展示では、建物の空間に入って動き回れるようなスケールへと展開されていた。小金井のほうは大きな映像が壁全面に投影されていて、そこを通じて向こう側の世界とつながっていくような感覚が導入されていました。昨年のCALM&PUNK GALLERYの個展(「Dirty Palace」展、2018)では、さきほどの別の世界が、そのままのスケールで三次元の場として出現してきました。
こうして見ていくと、じょじょにスケールが展開していってますが、これは意識的なものだったんですか?
振りかえってみると着々と変化してきています。愛知県立芸大の学部3年生のときに学内でやった個展で、空間的な展開の可能性に気づいたんです。あまりコンセプトなどもなく、ひとつのアイデアだけでオブジェクトや彫刻的な作品をつくっていたんですが、それを会場に配置していくという段階になって、「あっ、これは違うんだ」って。もので見せるのではなくて、それによってつくられた空間が展示だということに、そのタイミングで初めて気づいたんですね。
それまでは「絵画」とか「絵画的」みたいな言葉にもっと引っ張られていたんです。 どちらかと言うとそれまでも、ひとつのものをつくるというよりは、それがある状況を考えていたし、コンセプチュアルなオブジェクトにしていたわけではなくて、だからこそ「空間的な絵画行為」に引き寄せられていったんだと思います。
その後の卒業制作では、小屋のかたちの作品をつくりました。それは小屋であり、キャンバスでもあって、小屋の外に絵が描かれているんですね。キャンバスにボリュームを与えたら物理的な空間が生まれるから入れるというイメージです。すごく単純だけど、ファンタジーじゃなく本当に入れることが特別な体験だという考えがありました。それが自分のなかですごく成功した感覚があり、その後2年ほどはそういう作品をつくっていたんですが、でもやっぱり壁にぶち当たってしまった。そもそも絵画の道を志して極めていた身ではなかったので。


Photo by Tetsuo Ito Photo courtesy of Assembridge NAGOYA 2016
──大学では絵画を学んでいたんですよね?
油絵学科の出身ではあるんですけど、油絵は結局大学に入るきっかけでしかないんです。入学してからはほとんど絵は描いていなくて、卒業制作も、コンセプトのために必要だから描いたようなもの。
でも自分が絵画にとらわれていたのは確かで、絵画との距離感が、よくよく考えたらすごく不自然でした。 そういうときに、単純に絵の要素を削げばいいじゃんと思ったんです。それまで「空間的な絵画行為」というようなことにとらわれていたけれど、それ以前に空間的な作品をつくることに興味があると気づいたんですね。
つまり十分な小屋をつくることで、違う次元、違う空間をつくり、しかも入れ子状になっているという。そういう部分だけでいいじゃないかという思いから生まれた一番最初がswitch pointの展示です。だから本当は小屋をつくらないでいようと思っていたんですけど、あえてつくったんです。
──それはキャンバスの枠を三次元的に構築するような感覚でしょうか?
はい。自分がよくやっていることなんですが、今後の作品のためにつくる作品というのがあります。例えば、小屋の作品を何作かつくっていたときに、閉ざされた空間の中だけじゃ自分がイメージしているものには限界が来るような気がして、それを打破するために小屋をひっくり返したんです。 一度小屋の状態を提示し、今度はそのオモテとウラを全部ひっくり返した。床も逆さまになって、天井が外に出て。
そうすると今度は、小屋の外に描かれていた絵が内側にくる。するとそれが洞窟壁画みたいな空間になって、妙な広がりが生まれるなと。で、一回それをやったことで僕の空間はもう外に出た。というので、その次の藝大大学院の修了制作では小屋などはいっさいつくらずに、単純に空間にバーっと展開していったんです。
CALM&PUNKの作品も同様で、布という素材を使うことで拡張可能というスケール感も操作できるようなものになればなあと。ドレープも、実際は2メートルとか4メートルとかですが、外まで続いていても別に変わらないというか。横も広がっていくし伸縮するし、あえてちょっと薄い布を使っていたので透けるし。それでまた向こう側が生まれていくというのを得て、自分のなかでより自由度が上がってきています。すべてを説明しきれるわけではないんですけど、CALM&PUNKの展示を経たことで、すごく整理されている状態になりました。

Photo by Takamitsu Nii
宇宙的スケールへの展開
──映像は平面だし絵画と近い感覚があるのかな。ただ、映像とくに大画面のものは彫刻的な要素も大きいですよね。
映像をつくるときには、あまり絵づくりをしている意識はなくて、窓枠の中の景色ではなく、窓の向こう側の空間をつくろうとしています。アニメーションというよりは画像を動かすことによって映像が進んでいくというようなもので、パソコンでずっと作品をつくっていると、レイヤーに対してすごく不思議な気持ちになってくるんですね。レイヤー間に距離はないのに、でも確かに重なりはあるという。

──映像の要素でも、レイヤーの重なりを意識したものが多いですよね。
そうですね。映像の向こうに、あきらかにこっち側とは違う次元の空間が生まれているということです。まだその奥にもあるかもしれないんですけど、いまはまだ覗ける程度で。空間を拡張させるために、画面の向こう側にも空間を設定している。あとはあまり抽象的になりたくないという気持ちがあります。抽象的な部分に、個人的にあんまり作家性を感じないので。
──玉山さんの作品のモチーフとして、ミラーの回転や、振り子の運動が挙げられると思います。振り子などは、重力だけでなく地球の自転など、普段の生活では把握ができないスケールの運動を表しているのかなと。
それももともとイメージしていたわけではないのですが、自分の使う要素のなかで、あまりにもそういう円運動が多いんですよね。そこに複雑な動きなどは求めていなかったんですが、ロサンゼルスで展示(「Takuro Tamayama and Tiger Tateishi」Nonaka-hill、2019)したときにやっと気づきがあって。やっぱり回転させないといけない。 ロスでは、CALM&PUNKで展示した簡略化した人型ミラーを3Dにして大理石でつくり、それをモーターで回しました。それから、奇しくも日食などのイメージを作品に展開していて、この世界のベースになる円運動ともつながっていた。 イメージのなかでですが、ここで何か新しい宇宙的なスケール感を得たなと感じたんです。
──地平線が回転する映像も、ある遠点から見た地球の自転運動の表現でもありますよね。
まさにそうですね。人が簡単には認知できない動きみたいなものが、自分のなかに入ってきてるのかなとか、出していきたいなっていう気持ちがあって。それがあっての円運動だったのかなって自分で納得してきています。

Photo courtesy of Nonaka-Hill
世界の終わりのイメージと資本主義のその先
──もうひとつ作品のキーワードとして、「ヴェイパーウェイヴ(Vaporwave)」が挙げられるでしょうか。ヴェイパーウェイヴのイメージで頻出する、21世紀のハイパー資本主義の感性とでも呼べるような、レトロ・フューチャリスティックな80年代っぽいTVモニターや、パソコン黎明期のテクノロジーへの希望に満ちたギークたちがつくるゲームのローファイなイメージなど、そういったものを感じるんですね。
また、ヴェイパーウェイヴとはもともと、テクノロジー企業が発表する、発売されることのないソフトウェアなどを意味する、実態のない霧のようなものを指しています。そこも、玉山さんの過剰な色に満たされながら実体感の希薄な空間は、ヴェイパーウェイヴにおける「ヴァーチャル・プラザ」を連想させます。
純粋に、趣味としてもヴィンテージ的なものやダサいチープなイメージはすごく好きではあるんです。ただ、作品に対してそういう考えはなく、まずあまり現時代的なものを取り入れたくないんですよね。現時代的すぎるとやっぱり古いものになってしまうので。だったら古いものから引用したほうが、逆に新しさがあるのではと。
──さらに言うと、ニック・ランドらが提唱している「加速主義(accelerationism)」という思想も連想させます。これは、「資本主義の終わりより、世界の終わりを想像するほうがたやすい」という閉塞感に覆われた「資本主義リアリズム」をより激化させることで、その裂け目から新たな世界への出口を目指そうという、やや過激な思想です。
玉山さんは作品のなかで、深夜の通販テレビで宣伝される家電や掃除器具、セレブのイメージなどのモチーフがたびたび登場します。単純な流行りというのではなく、アーティストの時代をつかむアンテナが反応していて、そこに、この状況の先を見据えるヒントがあるかもしれないと感じています。
加速主義というワードは知らなかったんですけど、ロスのギャラリーのオーナーにも、そういうのをすごく感じるって言われました。たしかにそうだ、そのとおりだって、言われたことが全部、その言葉を通して理解できた気がします。 それって、楽観的とも違うじゃないですか。けどスタンスとしてはある種、そういう距離で見ているというか、たぶん社会に対しての距離ですよね。そこは自分の作家性にすごくある部分だと思います。
──例えば、玉山さんの作品にも出てくる「日蝕」は、いま僕たちは科学の力で、地球と月の公転による太陽と月の重なりで起きる現象という原理を頭で理解しているけれど、その原理がわからないかつての人類は、日蝕は世界の終わり(アポカリプス)だと信じられていました。ここにも自転と公転が出てきますが、こうした世界の終焉のイメージと資本主義の終着が交差するところに、玉山くんの作品はある。
社会的な構造に興味があるわけじゃないんです。でも今言われたことが的を得ているのはたしかで、映像のああいうイメージや人がまったく出てこないことにも、逆にそれでやっと説明がついてきたように感じています。
──唐突に聞いちゃいますが、これまでの人生の生い立ちで何か思い当たる節ってありますか?
なんですかね。これはあんまり関係ないかもしれませんが、なんかすごく次男的に生きてきたんですよね。長男の後ろ姿を見ながら、世の中をどうこうするというのは兄が担ってくれるだろうと思ってた。もともとそうやって、社会に距離を置いて見ていて、自分が当事者になっていなくて。幼い頃からそれが普通の見方だったんですよね。
──対象と距離を持って見るというのは、アーティストの重要な資質ですよね。
でも振り返ると自分が小学生のときにWindows XPが出て、そのときからよくわからない海外の通販サイトを見ていて、掃除道具屋のサイトでモップも見ていたんですよね。Bitで描かれてるような、いわゆるあの頃の雰囲気の。あのイメージのインパクトはすごく強くて、ものすごく魅力的だったんですね。思い返すと、当時パソコンみたいなテクノロジーっぽいのに興味が寄ったときも、「パソコンはすごい、なんでもできる」とかっていう世界にはいなくて。今っぽくない、いわゆる90年代的な雰囲気の部分に惹かれていたというか。
──玉山さんの映像と空間の関係を見ていると、虚構と現実に境界線を引いてないというか、映像の向こう側の世界と現実のこちら側の世界を同時に扱っているという印象があります。
向こう側とこっち側が等価値で、自然と同居させている感じですね。まだうまく説明ができないんですが、それができるようになってきたという手応えをたしかに感じています。 これまでは、いろんなメディアを使っていてもそこに説得力はなかったんです。でも今は、この部分は人に依頼してつくらないといけないとか、これは金属じゃないといけないとか、この塗装はペンキじゃだめだとか、そういうことが全部、構造化されてすごく確立されてきた。だから、イメージさえできればそのとおりになるというのが、今の感覚としてあります。
今回のパルコの展示は、ちょっと映像の雰囲気を変えました。これまではなんとなく物語めいてたんですが、今回は全部ぶつ切りで、かつリフレクションするというところに意識をもっていって、その中に世界が増殖していくような。 作家として今すごい、二面性を持ちたくなってきてるんですよね。それだけじゃない、という幅を。でも本質的な「虚構をつくる」というのは変わらないんですけど。
西洋美術史の終着点とロサンゼルス
──この夏にロサンゼルスで展示して、それがとても良かったとお聞きしました。アメリカの西海岸は、ヨーロッパから始まった近代が、大西洋を渡りアメリカ大陸に到達して、先住民を蹴散らしながら荒野を開拓していったその最果てなんですよね。なので、ここは近代や資本主義のどん詰まりで、そこに映画産業のハリウッドがあって、セレブの虚構のイメージこそがもっともお金になるという場所。その場所がまとう雰囲気や感覚が、玉山さんにすごく合ったのかな。
そうですね。正直、活動の拠点にしたいと真剣に考えているほどです。西洋の美術の終着点でもあるし、地理的に見たら西側は環太平洋でアジアがあるという場所で、その西洋の美術史にようやく自分も関与する方法としてロスに移住するというのがすごくまっとうなやり方だと感じています。
それはけして日本の美術に批判的であると言うよりは、自分のやりたいイメージに対して、日本にいてもそんなにつながっていくものが無いかなっていう気がしてしまうんです。どちらかと言うと、退けられてるくらいの気持ちがある。とくにここ最近、あいちトリエンナーレで起こった問題や乱発している社会的な問題を扱った美術館の企画展とかに、どうしても自分は寄り添う気になれない。

Photo courtesy of Nonaka-Hill
──なるほど。玉山さんの作品は、広く人類の歴史や文明というスケールで見るべきなんだと思う。そういえば、今回の展示は、紫色が多用されています。紫色って不思議な色で定義ができない。赤と青を混ぜると紫になるけれど、色の波長としては赤と青は両端なんですね。その両端の外側の曖昧な「霧のような波長(Vaporwave)」が紫色です。東と西のように、はみ出たエリアの色でもある。
よく作品について「色が重要なんでしょ」って言われるけど、どちらかと言うと僕の色の使い方って暴力的というかあまり愛情のあるものではないんですよね。好みで使い分けているだけという側面もありつつ、効果としても利用しているというところも大きくて。
今回使った紫色は、『GAS BOOK 35 TAKURO TAMAYAMA』(2019)の見返しにも使ったのですが、今後多用していくという表明でもあるんです。 ロスとNYで、マルティーヌ・シムズっていうアメリカ人の黒人女性のアーティストの作品を見たんです。アメリカという場所で黒人であり女性であり、という立場を軸に置いた作品なんですけど、単色でまとまったインスタレーションをしていた。紫なら紫、オレンジならオレンジという。しかもオレンジと紫ってどっちもすごく曖昧な色だと思うんです。それを圧倒的にかっこよくインスタレーションに使えていて。そこからいつもと違う角度で、色を試してみたいなと思っていて、今回の選択になりました。

Photo by Takao Iwasawa
──僕らが渋谷パルコの「OIL by 美術手帖」のオープニング展を玉山さんとやりたかったのは、2020年を目前にした東京・渋谷に新しくできる商業施設という資本主義の極北とも言える場所、しかもファッションフロアでギャラリーをやるなら、そこに拮抗するようなアーティストにお願いしたいなと。ハイパー資本主義のなかでのアートの立ち位置を測定できるような作品を見せたいと思ったんです。
海外のアーティストでは、ウルス・フィッシャーには近い感覚をみています。彼はもっと彫刻からのアプローチですが、ものやイメージの取り扱い方や、スケール感の操作が近いと感じます。
めちゃくちゃ好きですね。感覚が近いというより延長線上に彼がいる感じはします。 突き詰めたら、やっていることはあんまり変わらないかもしれない。彼のほうがより問題に対してわかりやすく扱っているというか、それが彼のらしさだと。なんかちょっとした品の無さとか。ある意味、彼がそうやってものすごくうまく扱っているがゆえに、アプローチの仕方として自分がそれをやるつもりはないんです。
本当は、空間的だけど物質的なウェイトが大きい展示ももっとしたくて。彫刻的なものとか。ウーゴ・ロンディローネがめちゃくちゃ大好きで。彼のようなものの扱い方とか、近い構造をもった作品の展開もしてみたい。ほんとはめちゃくちゃいっぱいあるんですよね、やりたいことが。
──ユーモアもあるしね。
ほんとはめちゃくちゃいっぱいあるんですよね、やりたいことが。それには相当な数の場が用意されていないとそっちに手が出せないですが。モップの作品をロスで展示してたんですけど、それが今、単体でアントワープに展示されていて。この出来事は別の展開のひとつの始まりなのかなと感じています。 今後ある程度キャリアが付くことで生まれる新しい説得力もあるだろうし、自由度の高い活動の仕方に憧れますね。
──今日はありがとうございました。海外を含めた次の展開を楽しみにしています。