青森5館連携トークイベントレポート。アートと地域との連携から考える、魅力ある青森とアートプログラムのこれから
青森県内5つの美術館・アートセンターが連携してその魅力を国内外へ発信する取り組み「AOMORI GOKAN」。「アート」のあり方と発信・連携のパラダイムシフトを提言するトークイベント「アート県『青森』の挑戦!! 第二弾」が弘前市内で開催された。

青森県は、県内にある5つの美術館・アートセンター(青森県立美術館、青森公立大学 国際芸術センター、弘前れんが倉庫美術館、十和田市現代美術館、八戸市美術館)が連携し、2020年に「青森アートミュージアム5館連携協議会」を創設、それぞれの特徴を生かしつつ、アートの新しい体験と青森の魅力を国内外へ発信するプロジェクト「5館が五感を刺激する―AOMORI GOKAN」(以下、AOMORI GOKAN)を進めている。
これまでWEBによる情報発信やフォーラムの開催などの活動を通じてプロジェクトの普及に努めてきたが、2021年八戸市美術館がリニューアルオープンし、いよいよ本格始動する。これに先立ち、2022年3月6日に第2弾となるトークイベントが、弘前市の旧弘前偕行社で開催された。

青森がめざすアートプログラムの取り組みと今後の展開、新たに開館した八戸市美術館のコンセプトと各種の活動の紹介に続き、アートと地域コミュニティとの“新しいかたち”の長期的な視野での青森の可能性について、フォーラムでの議論が交わされた。
協議会を代表して青森県立美術館館長・杉本康雄が、AOMORI GOKANの2021年度の活動とこれからの計画を紹介。青森にある5つの美術館はいずれも名だたる建築家が手がけた、その建物に特徴がある。それは、地域の持つ環境と歴史をふまえ、各美術館の機能を体現すべく造られており、それそれが個性的で、これだけでも見ごたえがある。これらの建築について、設計者による解説やコンセプトを見せていく企画が2021年度から始められ、WEB上で展開される。2022年度からは、加えて青森にある歴史的な建築にも注目、美術館にとどまらないツアーやワークショップなども計画されている。
弘前には、前川國男のモダニズム建築が残り、初期から晩年まで概観できる。本フォーラムが開催された旧弘前偕行社は、ルネサンス様式の貴重な明治期の近代建築として重要文化財にも指定されているもの。こうした青森の建築資産の活用に意欲を見せる。
そして、2024年の春から夏にかけて、5館による共通テーマでの企画を準備中。建築、所蔵品、支援方針など、各館の特性をひとつのテーマで見せていく展覧会の予定が発表された。
これらは、美術館を巡るだけではなく、県を横断、縦断する立地を活かし、移動の過程で青森の各町の持つ歴史、生活、文化に触れ、体験できるものとして計画される。点から面へ、過去から現在へ、いわば県全体でのアートフェスティバルとなり、「アート県『青森』」を強くメッセージするものとして期待が高まる。
次いで、昨年11月にオープンした八戸市美術館の紹介が、同館副館長・高森大輔よりなされた。
八戸市美術館の最大の特徴は、エントランスに設えられた「ジャイアント・ルーム」。広大なホールは入場無料、飲食も可能で誰もが使用でき、市民や来館者の憩いの場として機能する。特製のカーテンや仕切りで小部屋を作ることもでき、各種のイベントや会議、発表会などに使用される。学芸員の企画会議などもここで行い、見える、参加できる機会を醸成することで、地域との交流を深めることを企図している。

また、美術館活動に主体的に関わる市民を「アートファーマー」と呼び、様々な経験ができる環境をつくり出す。アートファーマーによる建築ツアーガイドでは、それぞれの自由な発想や感想を活かしつつ、会場での多様なコミュニケーションの促進を果たしているという。
耕し、育むことを意図し「出会いと学びのアートファーム」と名づけられたコンセプトは、「作品をみせる美術館」から「地域コミュニティの拠点」へ、学びと連携という、未来型の美術館としてその活動を開始している。
トークイベントでは、青森にとどまらないこれからの美術館が担うべき役割と可能性について、深い議論が展開された。キーワードは「内と外」。
モデレーターには、FEC(*1)設立者で、現在京都芸術大学の客員教授、アートフェアACK(*2)のプログラムディレクターも務める金島隆弘、パネラーとして、アーティスト・鴻池朋子、株式会社風景屋取締役・小林恵里、十和田市現代美術館館長・鷲田めるろが参加した。
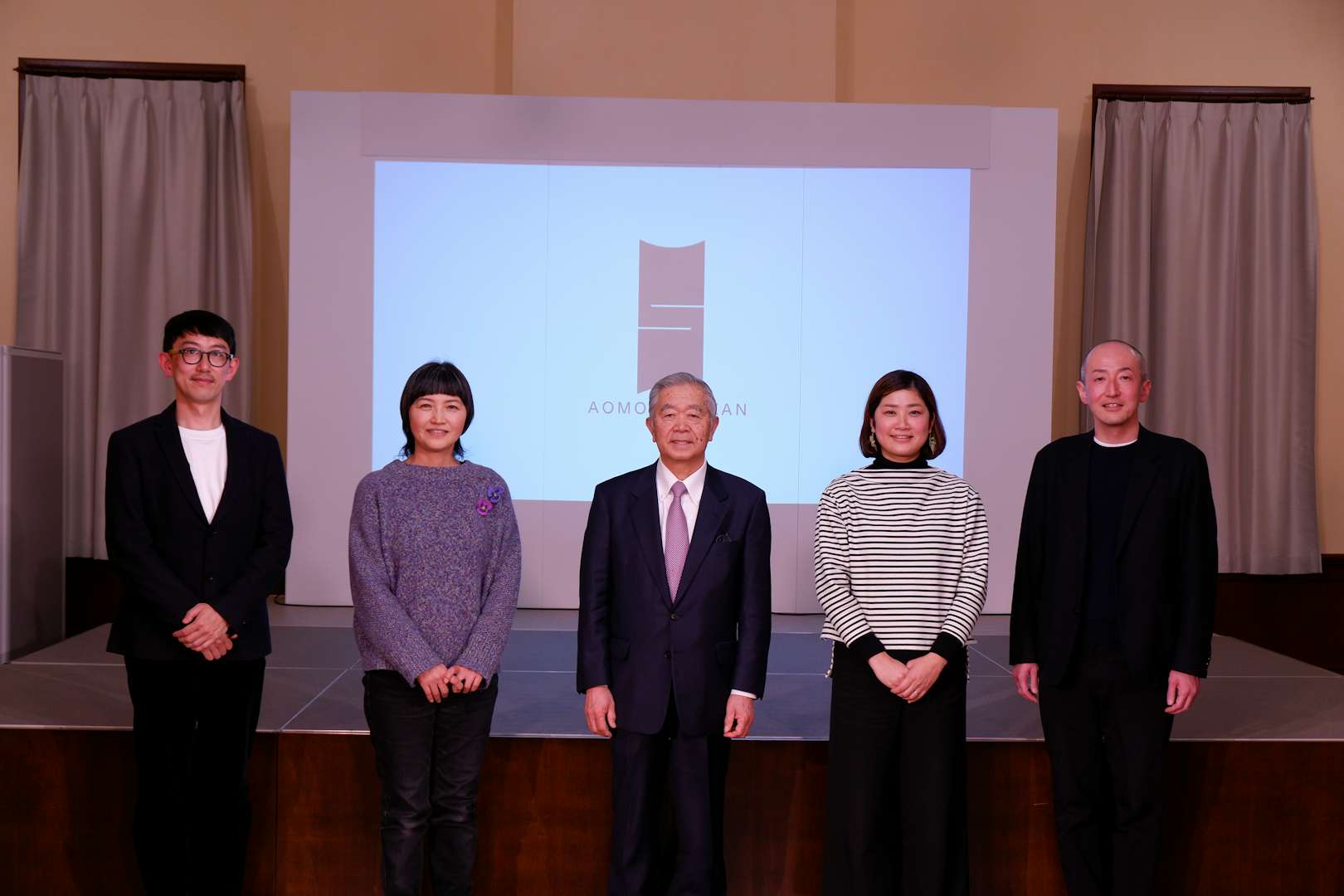
創る者、地域の活性化を担う者、そして美術館を運営する者、それぞれの立場から、その経験を通して、アートと地域のいま、そして未来へのあり方を語った。
絵画、彫刻、映像からパフォーマンス、絵本、手芸と、幅広いメディアで作品を生み出している鴻池は、自然と人間との関わりを「根源的暴力」ととらえ、人間の文化や芸術の根源的な問いを発信し続けている。
2020年に東京・アーティゾン美術館で開催された個展「ちゅうがえり」は、毎日芸術賞を受賞、現在も角川ミュージアムでの屋外展示をはじめ、国内外でいまもっとも精力的に活動しているアーティストのひとりである。
彼女は、青森に限らない根源的な話を、と前置きして、東日本大震災以降、展覧会で訪れる各地で独自にはじめたプロジェクトについて語る。

美術館を出て、個人的に地域の人々と出会い、個人的な歴史やエピソードを聞く。そこから一枚の下絵を描き、それを本人あるいは他の人に刺繍してもらってきた。「物語るテーブルランナー」と名づけられた創作は10年を経て、ようやく自身にも見えてきたものがあるという。
残らない、語られない個人的な歴史を刻むこと、その場こそが美術館となっているという感覚から、鴻池は、「美術館」という施設が、「宝」として作品を保管、守っているという現状に疑義を呈する。燻蒸され、守られ、ガラスケースに収まることが、みる者の感覚的な把握を阻害しているのではないか、との危機感につながった。
「動物としての人間は、その創造行為に常に破壊を伴っている。人間中心の考えから地球という存在からものごとを考える時代になったと思う」。
自身の創作も含めて、人間の営為がゴミを出すものとし、それを踏まえた上で、地球に還元される人間の創造を提唱する。それはみる者にも実感としてとらえられ、当事者として関わるもの、あるいは関与していくきっかけとしてのアートである。近代から続いてきた価値観は、いま、大きなシフトチェンジを迎えている、と語るその主張は厳しい批判とともに大きなチャンスの存在を訴える。
今年から国内各地で巡回が予定されている展覧会を鴻池は「リレー」と称し、各館の学芸員がすべての展覧会に関わりながら展開することを計画中。そこでは、それぞれの所蔵品と同時に彼女が造る動物の糞(模型)が展示される予定だという。人間以外の生物の象徴として提示される動物の糞は、人の痕跡としてのアートと、動物の痕跡としての排出物を等価に見せ、自然界への通路を開くことを企図している。
「これまでを否定するのではなく、いまあるものをその先へとつないでいく、これからの美術館はその回路を開き、残し方を考える場として機能していくことが求められるのではないか」。

鴻池と深く共鳴するものとして、小林が語ったのが、現在彼女が暮らす十和田市における活動だ。
震災後、石巻における「リボーンアートフェスティバル」の立ち上げに関わったことを契機に、東京から東北へ移った小林は、夫の主宰する環境デザインを手がける風景屋ELTASに参画、十和田市に移住し、そこで長期滞在型のゲストハウスを運営しながら、町の活性化につながるプロジェクトを企画している。
世界でも珍しい二重カルデラ湖で、山手線の内回りとほぼ同じ円周を持つ雄大な十和田湖は、四季折々の色彩の移り変わりが豊かな地。その一角、彼女が暮らす人口200人ほどの集落は、観光地として年間100万人を迎えるも、冬場は公共バスも運休となる環境にある。近年は移住者やUターン者も増えつつあり、小林は彼らとともにプロジェクトを推進している。

活動には3つの方針がある。①十和田の大自然を大切にする、②消費される観光から環境に負担をかけない持続可能な地域へ、③美しい風景とともに、人びとの暮らしと文化を後世に継承する。彼女も近代以降の「消費」の限界を感じ、自然と人間との共生から新たな「観光」あり方を模索している。
現在は「北奥文化祭」を準備中。アーティスト・島袋道浩をキュレーターとして招聘し、アートと暮らしを体感してもらう様々な催しを企画しているという。
「マルシェや勉強会など、大きなことではなく、小さなことから、これまでの活動を複合的に見せたい。十和田は有名な観光地といいながら、ほとんどの人が慌ただしく通り過ぎていく。こちらのことばで“ここちよい”、“ゆったりする”を意味する“あずましい”をコンセプトに、ゆっくり過ごしてもらい、来訪者数のような数値では測れない、それぞれが何を、どのように感じ、受け取ったのかを重視したい」。

地域におけるアーティストの創作に、民俗学のフィールドワークに近い掘り起こしと文化を学ぶ作業を見て取った小林は、その地から内発的に発見、見出されたものを積み上げて、人々のものの見方や価値観を変えるのがアートの力ととらえ、そこに地域活性化への可能性を感じている。
こうした美術館、アートへの期待を受けて、鷲田は、美術館を運営する立場から、これからの美術館が持つポテンシャルについて述べる。
金沢21世紀美術館、あいちトリエンナーレ2019のキュレーターを経て、十和田市現代美術館の館長となった鷲田。ホワイトキューブの美術館といいながら、収蔵庫を持たず、町なかにも展示が展開される、開かれた造りを持つ同館の独自性を伝えつつ、就任後にコロナ禍に入ったことも相まって考えていることを語った。
「様々な制限がかかるなか、いわゆる“企画展”ではなく、美術館が“持っているもの”をいかに活用するかを改めて考える契機になった。そしてこの美術館と町の人々との関わりの濃密さ、来館者の7割が県外からきていること、この3つをつなげることができないか、と」。

作品、地域、来館者の相互作用に美術館の可能性を見いだす。収蔵庫から町へ、その展示では関わった人々が自身の経験とともに自分のことばで作品について語る。アーティスト本人の語りや学芸員の解説と併せ、こうした彼らの語りの機会を設け、支援していくプログラムも稼働している。それらは新たに学ぶサイクルになり、内と外がつながっていく。また、地元に継承される踊りを普及させる活動も協働、そこには現代の身体感覚による動きも加味されて、新しいかたちも生み出しているという。
キュレーターとして芸術祭にも関わった鷲田は、美術館におけるキュレーションと芸術祭におけるそれの分断を指摘する。各開催館の学芸員の企画力を活かした「会場」と「キュレーション」との連携のあり方、そして芸術祭の成果がコレクションとしてその地に残されていくことが課題だとする。
SNSなどネットの環境の高度化により、いまや誰もがアーティストとなり得る時代。その創造は破壊とゴミの発生を伴う。だから「創らない」ではなく、それを還元していく、解決していくために知恵を出し合う。
地域との連携も、その土地に暮らし、風土のなかでいかにあるべきなのか、ある程度の長いスパンのなかで、見えてくるもの、つないでいけるものをすくいあげることが求められる。
そのなかで、「完成品をみせる」という美術館のあり方を見直す。それもまた収蔵する/しないの二者択一ではなく、みる者が(メイキングや技法といった説明ではなく)作品の生成までの時間や思考へ想いをはせるきっかけを作っていくこと。創造と鑑賞・消費の仲介的なシステムとして機能すること。
各地でアートフェスティバルのディレクターを務める金島が実感するように、何年も開催地に過ごしてこそ見えてくるものは多い。
「既存のシステムのなかで、アートが持つやわらかな思考や、固定概念をくつがえす契機を創出すること、これがこれからの美術館に、そして地域との連携の中に期待される」。
美術館の連携、地域社会との関わり、そして長期視点での方向性。内から外へ、外から内へ、時空を超えた要素を多彩に持つAOMORI GOKANはそのポテンシャルを内包している。
行政との調整や各地との連携に課題も多い。もちろん、一気に実現することはできない。だからこそこれからプロジェクトが進む先に希望を託したい。
*1──Far East Contemporaries。金島が代表を務める21世紀を迎えた東アジアで活躍するアーティストのためのクリエイティブ・プラットホーム。2007年から活動中
*2──Art Collaboration Kyoto。2021年から国立京都国際会館で開催されている新しいかたちのアートフェア








