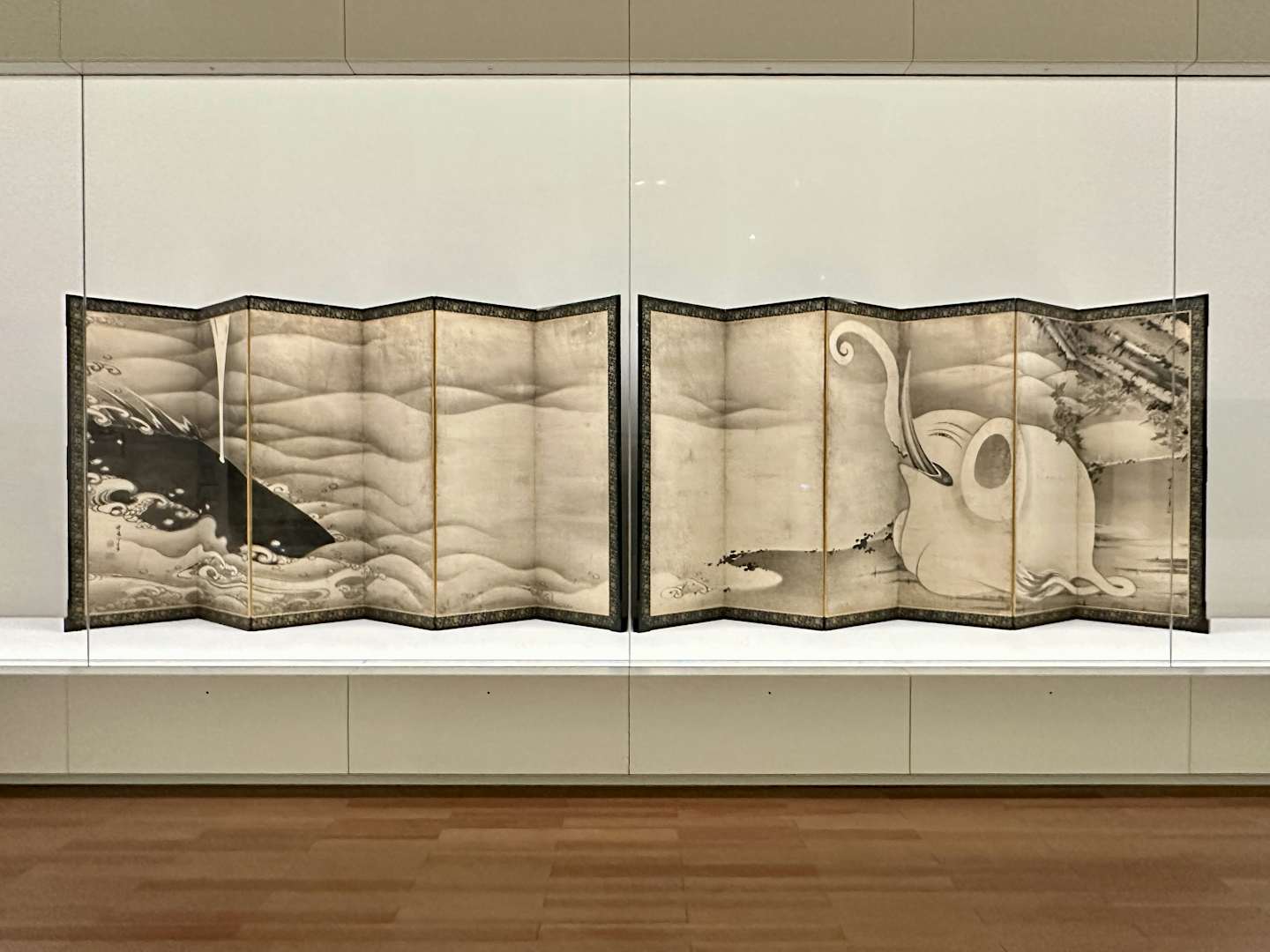「アート・オブ・ザ・リアル 時代を超える美術ー若冲からウォーホル、リヒターへー」(鳥取県立美術館)開幕レポート
3月30日に開館した鳥取県立美術館。こけら落としを飾る「アート・オブ・ザ・リアル 時代を超える美術ー若冲からウォーホル、リヒターへー」が幕を開けた。会期は3月30日〜6月15日。

日本でもっとも人口が少ない県である鳥取県に、新たな美術館「鳥取県立美術館」(館長:尾﨑信一郎)が開館した。
同館は1972年開館の鳥取県立博物館から美術分野を独立させたもの。設計は槇総合計画事務所と竹中工務店のジョイントベンチャーが手がけた。位置するのは、鳥取県中央部にある城下町・倉吉市だ。市立図書館が入る倉吉パークスクエアと山陰初の仏教寺院であり国指定史跡の「大御堂廃寺跡」に隣接する場所に構える。美術館はこの立地ならではの、南側に開かれた建築が大きな特徴となっている。

建物は地階なしの3階構造。敷地面積は1万7892平米、建築面積は5347平米、延床面積は1万598平米。館内の中心には全フロアを縦に貫く高さ15メートルの巨大空間「ひろま」があり、特別展示コーナーを含めると7つの展示室を擁する。コンセプトに「OPENNESS!」を掲げるだけに、館内にフリーゾーンが多いことも特徴だ(建築の詳細なレポートはこちら)。