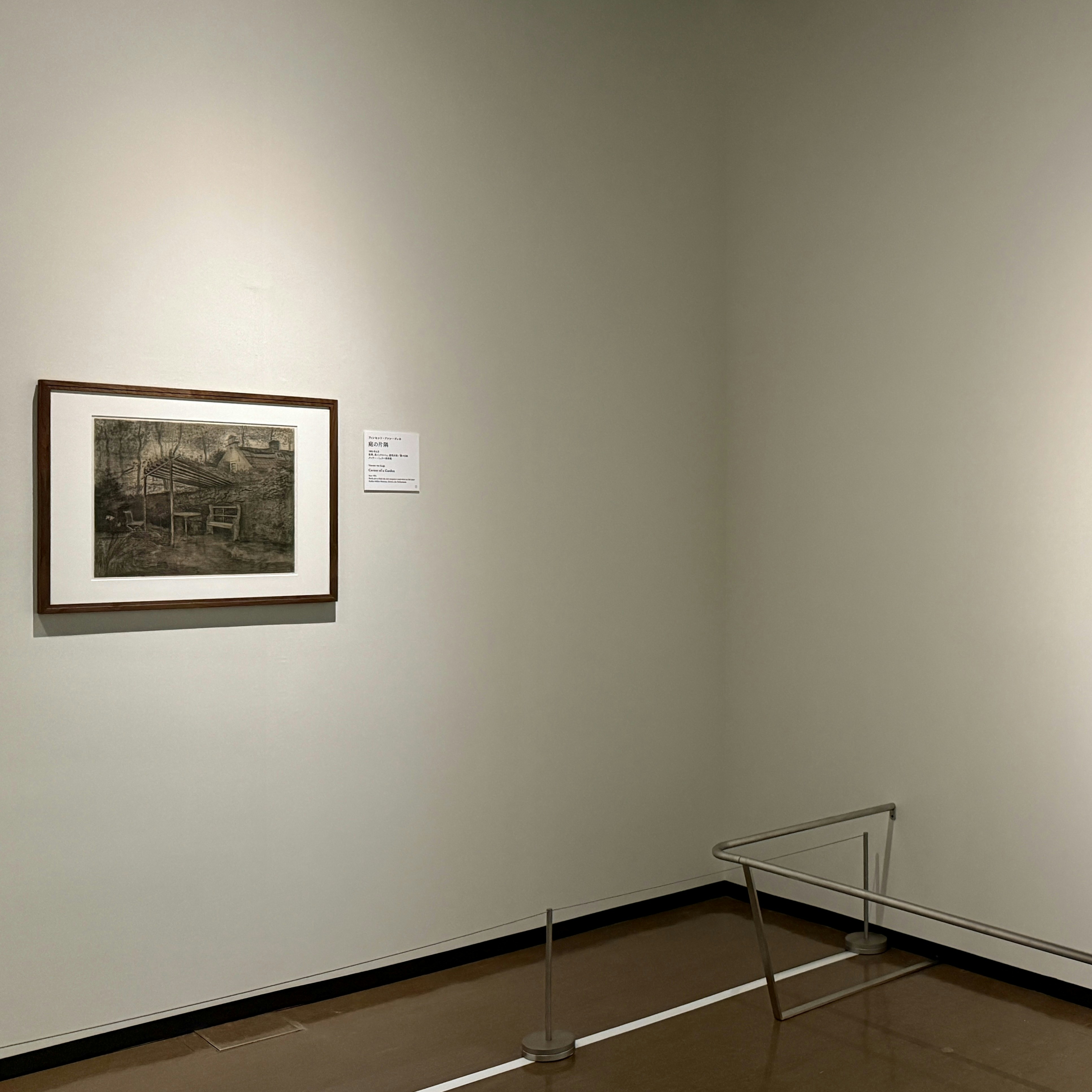「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」(神戸市立博物館)開幕レポート。20年ぶりに日本公開される名画とゴッホの軌跡をたどる
阪神・淡路大震災から30年を迎える今年、神戸市立博物館で「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」が開幕した。オランダのクレラー=ミュラー美術館の所蔵品から、ファン・ゴッホの名作57点と同時代の画家による17点が出品されている。会期は2026年2月1日まで。

阪神・淡路大震災から30年の節目にあわせ、神戸市立博物館で「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」が開幕した。
本展は、オランダのクレラー=ミュラー美術館が所蔵するファン・ゴッホの珠玉のコレクション57点と、同時代の画家たちの作品17点を紹介するもの。担当学芸員は神戸市立博物館の塚原晃である。
クレラー=ミュラー美術館は、ファン・ゴッホの油彩画約90点、素描約180点を所蔵する世界有数のゴッホ・コレクションを誇り、その規模はアムステルダムのファン・ゴッホ美術館に次ぐ世界第2位を誇る。
本展では、ゴッホの数ある作品のなかでもとりわけ知られる名画《夜のカフェテラス(フォルム広場)》(1888)が20年ぶりに日本で公開されている。また同作はこの20年間、オランダ国外に貸し出されることは一度もなく、極めて貴重な機会となっている。
会場は5章構成。第1章「バルビゾン派、ハーグ派」では、ゴッホが画家を志す初期に大きな影響を受けたバルビゾン派とハーグ派の画家たちを紹介する。画商の社員として若くしてパリやロンドンに勤務し、海外の芸術に触れていたゴッホは、1880年以降、本格的に画家を目指すようになると、農村生活を主題としたバルビゾン派の巨匠ジャン=フランソワ・ミレーを最高の画家として敬愛した。加えて、ハーグで活躍したヨーゼフ・イスラエルスらの作品にも強い刺激を受けている。
会場には、ミレー《グリュシー村のはずれ》(1854)や《パンを焼く女》(1854)、イスラエルス《ユダヤ人の写本筆記者》(1902)といった作品が並ぶ。ミレーが描く農民の逞しくも誠実な姿や、イスラエルスによる重厚な明暗表現を理解することで、ゴッホ自身の表現の軸が形成されていったことがうかがえる。