【シリーズ:BOOK】
「現代アート」を問い直す批評の実践。『アートートロジー 「芸術」の同語反復』
『美術手帖』の「BOOK」コーナーでは、新着のアート&カルチャー本から注目の図録やエッセイ、写真集など、様々な書籍を紹介。2019年6月号の「BOOK」2冊目は、クロスジャンル的に活動する批評家・佐々木敦が2017〜18年の展覧会、公演、書籍、映画などを通じて「現代アート」を問い直す『アートートロジー 「芸術」の同語反復』を取り上げる。
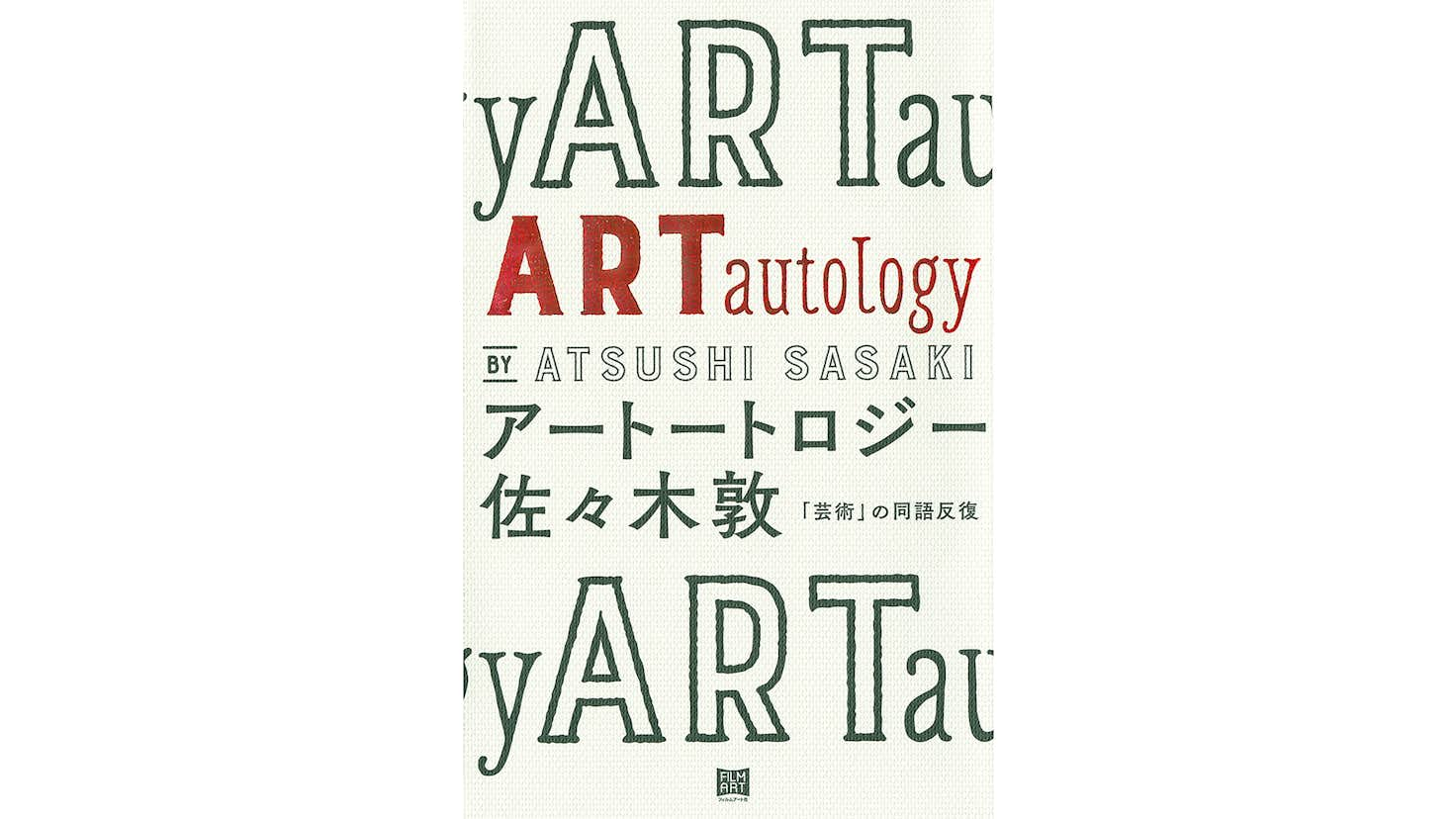
凝り固まったアート観をほぐすために
トートロジーは厄介だ。私を私たらしめているものは何か、という終わりなき問い。あるいはAはAであるという身も蓋もない言明。そばにはブラックホールのような深淵が控えていて、問いかける主体を時に虚無へと誘う。芸術をめぐる存在規定も、近代以降、この手のトートロジーから逃れられずにきた。マルセル・デュシャンがどこにでもある男性用便器を《泉》と名付けて美術館に展示したのは1917年のこと。それから1世紀も経過するというのに、「アートは(それがアートと表明されたから)アートである」というトートロジーは依然として解決しきれていない。
デュシャンを本流とする悪しき循環構造を「アートートロジー」なる造語で呼ぶ著者は、ここからさらに歩みを進め、トートロジーを現在(進行)形で批判するという課題に挑む。著者によればトートロジーにもポジティブな作用とネガティブな結果がある――だからこそ、批評はその評定作業を逐一行わなければならない。その試みは、空転するトートロジーに抗して作品やアートをめぐる事象に個別具体性を与える作業と見なすことができるだろう。
文芸誌での連載を単行本化した本書は時評集の趣を持つ。上妻世海がキュレーションした「世界制作のプロトタイプ」展に演劇的機能を見出し、奥村雄樹やミヤギフトシの映像作品を介して「私」の語りを可能とさせるナラティブの技法を探り、2017年の札幌国際芸術祭をモデルとして芸術の有用性を問う世間の論調に疑義を呈するなど、クロスジャンル的に活動する著者ならではの広い視野が活かされている。現代美術のクリシェに従わない刮目すべき作品やイベントが動態的な筆致でとらえられるなかで、トートロジーのその先も少しずつ予感されてゆくかのようだ。
近年の話題が多いなかで異彩を放つのは、3章分を費やしたマイクロポップの再考だろう。松井みどりが提唱した理論にニコラ・ブリオー『関係性の美学』との相似性を見出す視点は興味深いものであり、かつ、マイクロポップが持ちえた遊戯的な抵抗のモードがなぜ廃れてしまったのか、現代日本の状況と照らし合わせて検証するための有意義な論点を提出している。
トートロジーを外部から眺める傍観者ではなく、ともに制作者のひとりとしてトートロジーを体感し、作品の個別具体的な単位から現在と未来の展望を組み立てること。括弧つきのアートに具体的な手触りを取り戻すべく、粘り強く挑んだ成果がここに結実した。
(『美術手帖』2019年6月号「BOOK」より)