書評:展示空間から戦後芸術史を読み解く。『鈍色の戦後』
雑誌『美術手帖』の「BOOK」コーナーでは、新着のアート&カルチャー本から注目の図録やエッセイ、写真集など、様々な書籍を紹介。2021年6月号の「BOOK」2冊目は、美術だけでなく建築、デザインの分野も含めた「展示空間」から戦後日本の芸術史を検証する『鈍色の戦後』を取り上げる。
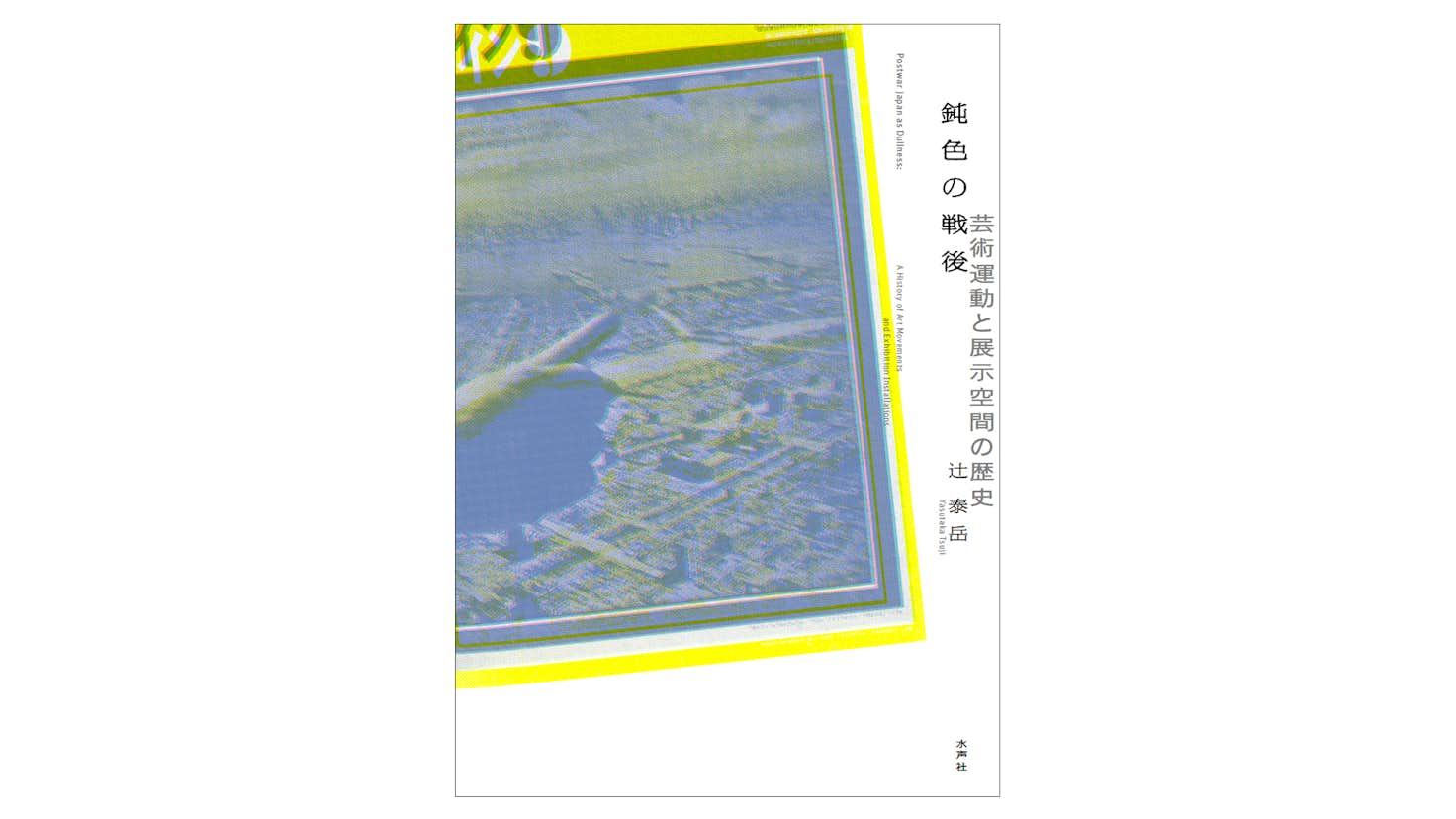
戦後芸術史研究はまだ終わっていない
1940年代から70年代前後の芸術運動を考察するにあたり、著者は戦後日本の像を「鈍色(にびいろ)」に喩える。気障なグレーでも雰囲気重視の薄墨色でもない、重さと冴えなさをまとった鈍色。通常なら主役になりそうもないこの色を表題に掲げたのは、鈍色が古来より喪の象徴であったこともおそらく関係する。著者いわく、戦後という区分の史的研究はまだ一段落していない。完全に葬り去られていない時代精神(ツァイトガイスト)のひび割れた声を、芸術史の深層からすくい上げる必要があるのだ。
そこで本書は、美術史のみならず建築やデザインの分野まで裾野を広げ、「伝統」「デザイン」「環境」といった鍵語が当時の作家や評論家の共通の論点であったことに着目し、ジャンルを超えた、しかし顕在化しにくい共同の姿を幅広く観測する。このときモデルケースとなるのは時代精神の体現者としての美術家や建築家個人ではなく、その都度仮設的に現れては立ち消えていくエフェメラルな展示空間そのものだ。52年に開館した国立近代美術館が戦後日本の足場を固める態度表明としてディスプレーを構成してきたこと、丹下健三が会場設計した55年の「メキシコ美術展」が非西洋圏の眼差しを介して日本の「伝統」を発見させる混淆的な場であったこと、66年の「空間から環境へ」展が70年の大阪万博に先駆けて「環境」という論点を世に問うたこと。物理的な構造体としての展示空間に言説・文化・技術の不可視の諸力を縦横に読み込んでいく分析は、視線が向かいやすい主稜線をあえてはずれ、旧来の史的研究が重視してこなかった展覧会や陰のキーパーソンにあたりをつけながら群像劇を描いていく。
他方、展示空間の成立を著名な建築家や企画者の手柄に帰する作家主義、作品の自律性を信じて疑わない近代的作品観に本書はくみしない。美術館を彩る収集品が文化政策を背負う外交の問題と切り離せないように、展示空間は社会や政治の動きと不可分に立ち現れるからだ。個々のモデルケースを重視した本書ではそこまで大きく踏み込んではいないが、展示空間に政治を重ね見る方法論は、国家という大きな枠組みの再検証にも及びうる点で画期的だ。
時代精神の正体を見極めるためには、メタ的な視点に立って指揮棒をふるう特権的な誰かに照準を合わせるだけでは十分でない。著者は会場設計の図面や調書を精査する地道な作業から始め、展示空間を集合的無意識の場として読み直した。俯瞰をやめて、未踏の原野へ。運動の伏流を追って戦後の像を解体・再編成した本書は、戦後芸術史の新たな見取り図を確かに示している。
(『美術手帖』2021年6月号「BOOK」より)