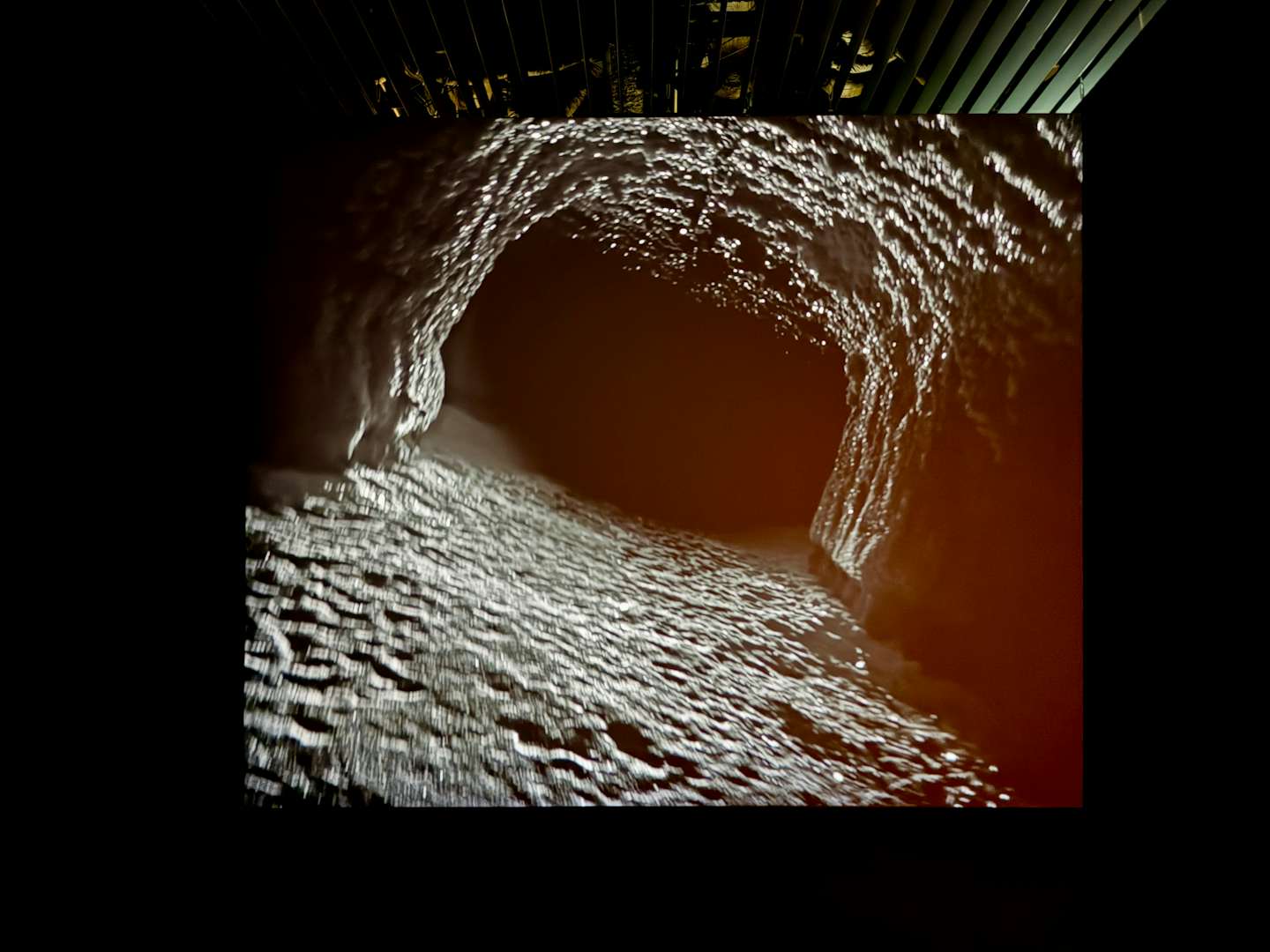「六本木クロッシング2025展:時間は過ぎ去る わたしたちは永遠」(森美術館)開幕レポート。多層化する時間に宿る永遠を問う
森美術館による3年に一度の展覧会「六本木クロッシング」が、8回目の開幕を迎えた。「時間」を中心テーマに据えた本展では、21組のアーティストの作品が紹介。その様子をレポートする。

森美術館で、3年に一度のシリーズ展「六本木クロッシング2025展:時間は過ぎ去る わたしたちは永遠」が開幕した。会期は2026年3月29日まで。
本展は2004年の開始以来、日本の現代アートシーンを俯瞰する定点観測的な役割を担ってきた。第8回目となる今回は、森美術館のキュレーターである徳山拓一と矢作学に加え、レオナルド・バルトロメウス(山口情報芸術センター[YCAM]キュレーター)とキム・へジュ(シンガポール美術館シニア・キュレーター)というアジアを拠点に国際的に活動するゲストキュレーター2名を迎え、「時間」を主要テーマに全21組のアーティストを紹介する。
本展の副題は、インドネシアの詩人サパルディ・ジョコ・ダモノの詩から引用された。「過ぎ去る時間」と「永続するわたしたち」という対照的な言葉は、時間に囚われながらも、その瞬間に永遠性を見出すという詩の主題と呼応する。
森美術館館長の片岡真実は開幕にあたり、「日本の現代アートを俯瞰する本展を実施する意義を強く感じており、日本とは何か、日本の現代アートとは何かをあらためて考える必要がある」と述べ、緊張と分断が深まる現代において、多様な視点を招き入れることの重要性を強調した。
また、徳山は「速度と効率が優先される社会のなかで、深く感じ、じっくり考える時間を取り戻したい」と語り、作品を通じた「多層の時間への眼差し」が展覧会の根幹にあることを示した。
本展では、日本にルーツを持つアーティスト、日本に在住する海外作家、海外在住の日本人作家など、多様な背景を持つアーティストを積極的に紹介している。全21組のうち半数以上がこうした越境的な存在で構成され、日本の現代アートを多角的に見つめる試みとなっている。展覧会は4つのキーワードで構成される。