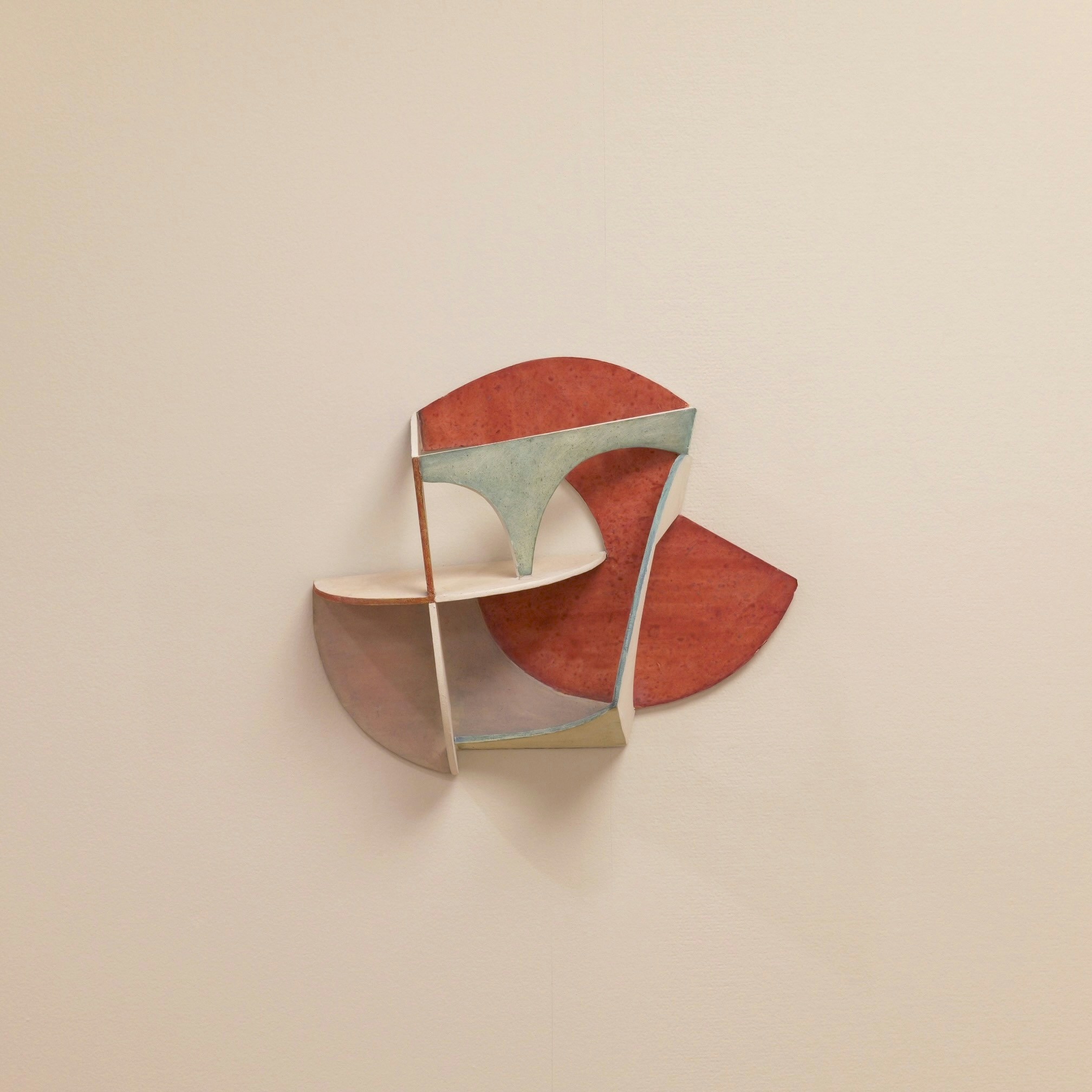「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」(東京都現代美術館)開幕レポート。「転回」の先に見えたその造形の到達点
岡﨑乾二郎の東京では初めての大規模個展「而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」が、東京・清澄白河の東京都現代美術館で開幕した。会期は7月21日まで。

岡﨑乾二郎の東京では初めての大規模個展「而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」が、東京・清澄白河の東京都現代美術館で開幕した。会期は7月21日まで。担当は同館学芸員の藪前知子。

岡﨑は1955年東京生まれ。1982年パリ・ビエンナーレ招聘以来、数多くの国際展に出品してきた。展覧会のみならず、ほかにも総合地域づくりプロジェクト「灰塚アースワーク・プロジェクト」の企画制作、「なかつくに公園」(広島県庄原市)等のランドスケープデザイン、「ヴェネツィア・ビエンナーレ第8回建築展」(日本館ディレクター)、現代舞踊家トリシャ・ブラウンとのコラボレーションといった芸術活動を展開してきた。教育活動にも取り組んでおり、芸術の学校である四谷アート・ステュディウム(2002~2014)を創設、ディレクターを務めた。2017年には豊田市美術館にて開催された『抽象の力―現実(concrete)展開する、抽象芸術の系譜』展の企画制作を行い、2019〜20年には同美術館で大規模な個展「視覚のカイソウ」を開催している。