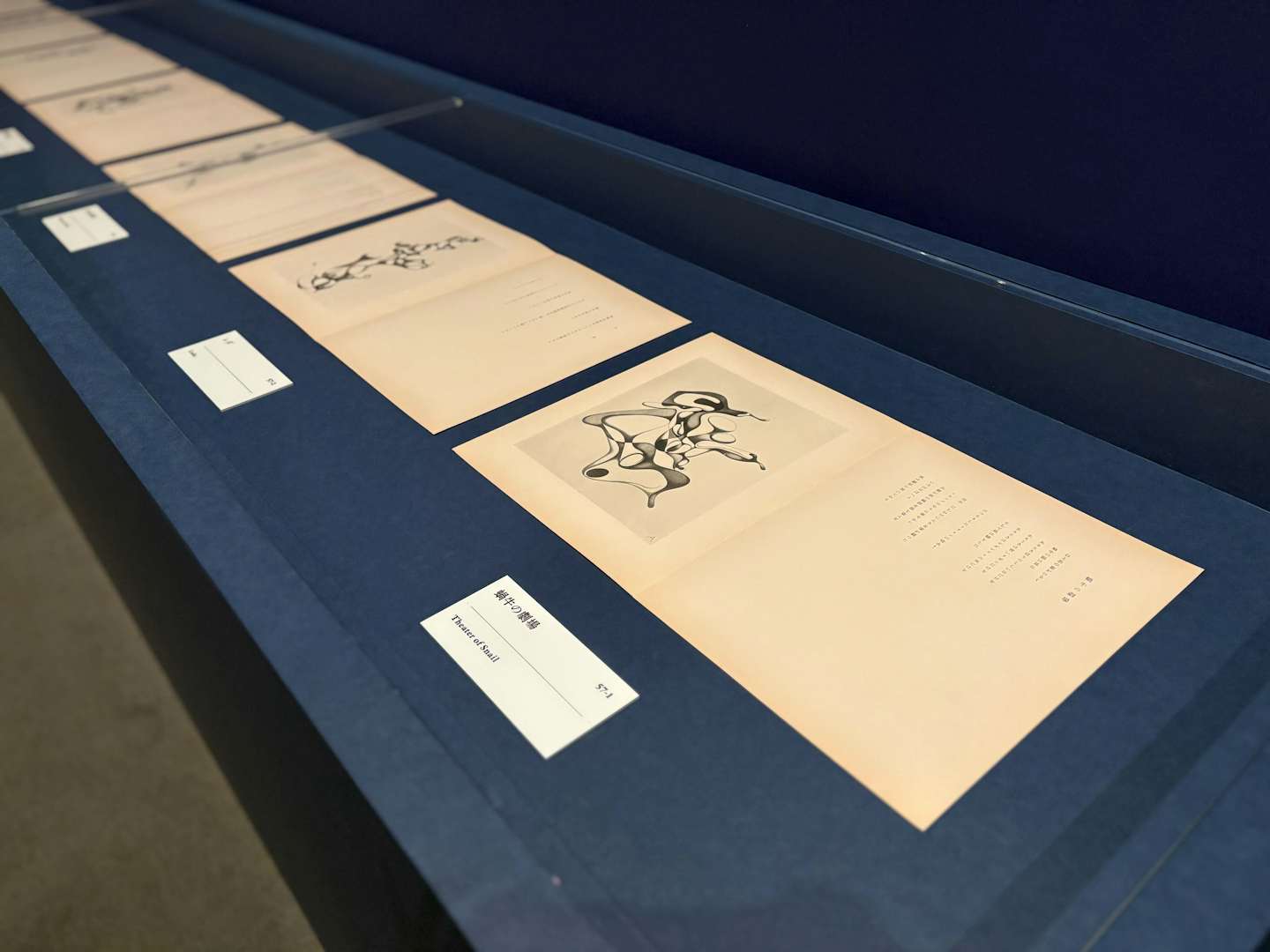開館50周年記念「モダンアートの街・新宿」(SOMPO美術館)開幕レポート。新宿ゆかりの芸術家たちの半世紀にわたる軌跡をたどる
東京・新宿にあるSOMPO美術館で、開館50周年記念「モダンアートの街・新宿」が開幕した。会期は2月15日まで。

東京・新宿にあるSOMPO美術館で、開館50周年記念「モダンアートの街・新宿」が開幕した。会期は2月15日まで。担当学芸員は古舘遼(SOMPO美術館学芸員)。
1976年7月、新宿に開館したSOMPO美術館。本展は、同館の開館50周年を記念して開催される、「新宿」をテーマとした展覧会である。明治時代末期の新宿には、新進的な芸術家が集まり、近代美術の大きな拠点のひとつとなっていた。中村彝、佐伯祐三、松本竣介、宮脇愛子など、新宿ゆかりの芸術家たちの約半世紀にわたる軌跡をたどる、新宿の美術館としての初めての試みとなっている。
本展は、4つの章と2つのコラムから構成されている。各章ではキーパーソンが立てられ、時代を下るようにそれぞれが紹介される構成となっている。
第1章「中村彝と中村屋 ルーツとしての新宿」では、1909年、相馬愛蔵・黒光夫妻が新宿に本店を構えた中村屋に集う作家たちと、その中心的存在であった中村彝に焦点が当てられる。中村屋には、ロダンに大きな影響を受けた彫刻家・荻原守衛(碌山)をはじめとする多くの新進芸術家たちが集まり、「中村屋サロン」がつくられた。この「中村屋サロン」は日本の近代美術史におけるルーツのひとつとも言える。
中村彝は荻原のもとに通い、それをきっかけに中村屋に集う作家との交流機会を得ていた。体調悪化により外出がまともにできなかった中村彝が創作の探究に力を入れたのは静物画であり、下落合のアトリエで制作された静物画の代表作《カルピスの包み紙のある静物》が会場で紹介されている。外光がよく入るアトリエだったことから、全体的に明るい印象の作品となっており、相馬愛蔵からの見舞い品であったカルピスが描かれている。また初期から晩年までの自画像も紹介されており、中村彝の画業を広く知ることができるような内容となっている。


続いて、1つ目のコラム「文学と美術」が展開される。文学と美術の切っても切り離せない関係に着目し、新宿ゆかりの作家を描いた肖像画や、文学者と画家との交流をうかがわせる作品が紹介されている。当時の文学を語るうえで欠かせない存在のひとつに、1910年に創刊された雑誌『白樺』が挙げられるだろう。西洋美術を見る機会が少なかった当時、カラー図版でそれらを紹介したことで、セザンヌやファン・ゴッホといった西洋の芸術家たちへの注目を促した。そんな『白樺』の中心的な存在のひとりだった武者小路実篤を岸田劉生が描いた《武者小路実篤像》も紹介されている。


また、小泉清による《向日葵》も本コラム企画の目玉のひとつと言えるだろう。読売新聞社主催の第1回新興日本美術展に出品された作品だが、学生時代に実篤宅で見たファン・ゴッホの《ひまわり》を意識したものである。《ひまわり》を収蔵する同館とのつながりも感じられる。